
2025.10.24
採用ブランディングの成功事例15選!失敗事例も紹介
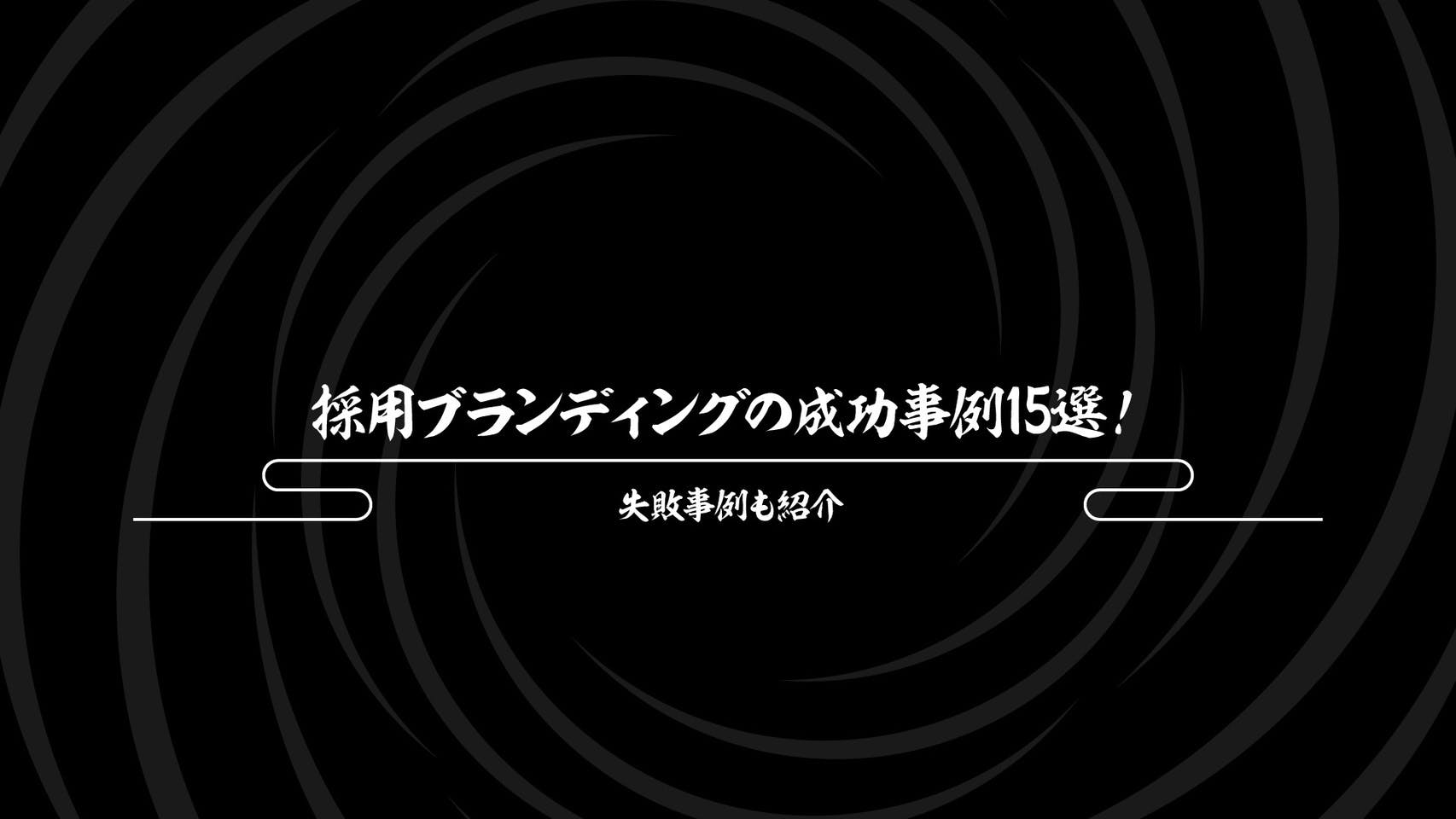
優秀な人材の確保には「給与」や「福利厚生」だけでなく、企業の価値観や文化への共感が欠かせません。採用ブランディングを強化することで、共感を軸にした採用活動へと転換し、長期的な組織づくりを実現する企業も増えています。
本記事では、採用ブランディングの成功事例と失敗事例を紹介します。
【大手企業】採用ブランディングの成功事例

これから紹介する各社の共通点は、自社の強みや価値観を可視化し、EVPやデジタルコンテンツ、動画、SNS、メディアを戦略的に組み合わせている点です。 データドリブンな分析でPDCAを高速回転させ、応募者のエンゲージメントを高めることで、定着率向上や応募数増加といった具体的成果を獲得しています。
ここでは、大手企業の採用ブランディングの成功事例を紹介します。
日本マクドナルド|EVP導入で従業員満足度を向上し離職率を低下
日本マクドナルドは、採用ブランディングの要としてEVP(Employee Value Proposition)を導入し「企業が従業員に提供する価値」を軸に据えています。
給与や賞与だけに依存せず、ブランドやカルチャー、人間関係、成長につながるスキルを言語化して発信することで、働く意味を具体的に示しています。
また「ピープルビジネス」を掲げ、多様な人材が自分らしさを認め合いながらワンチームで働ける仕組みを整え「あなただから動かせる心がある」というメッセージで内外の認識をそろえています。
こうした取り組みにより、従業員満足度が高まり、離職率を下げる効果が生まれ、結果としてエンゲージメントと組織全体のパフォーマンス向上につながっています。
三菱UFJ銀行|社員の働き方を可視化し多様な業種への認知を拡大
三菱UFJ銀行は、採用ブランディングの強化を目的に、キャリア採用の情報発信を拡充しています。
採用支援サービス「talentbook」を導入し、システム・デジタル領域など多様な職種で働く社員のリアルな業務や挑戦を記事・動画で可視化することで、求職者への認知を広げています。
さらに、オウンドメディア「金融のど真ん中で、プロになる。」をブランドカラーのレッドで統一し、自社の取り組み、キャリアプラン、募集情報を分かりやすく整理することで、検討度の高い候補者が迷わず応募に進める導線を整備しています。
併せて「セレクト時差勤務制度」や在宅勤務、サテライトオフィスの活用を進め、柔軟な働き方を実現しています。これらの取り組みにより、同社は金融の枠を超えた多様な職種の魅力を一貫したメッセージで伝え、認知拡大と応募転換の双方を高めています。
メルカリ|オウンドメディア「mercan」で入社後のミスマッチ防止を実現
メルカリは、採用ブランディングを担うPeople Brandingチームがオウンドメディア「mercan」を運営し、社員インタビューやプロジェクトの舞台裏などのコンテンツを年間300本以上発信しています。
独自の視点とリアルな声にこだわることで、単なる企業紹介に終わらない情報を届け、候補者が「メルカリの人はこういう価値観で働いている」と具体的にイメージできる状態をつくっています。
結果として、入社後のミスマッチを未然に防ぎやすくなり、採用ブランディングの効果を組織全体に波及させています。
さらに、社内勉強会や研修情報をまとめた社内Wiki「Mercari Quest」を運用し、知識共有を促進しています。透明性の高い情報発信を継続する姿勢により、社内外の情報ギャップが縮まり、候補者体験の質の向上にもつながっています。
三井住友銀行|採用活動の早期化とWEB活用でインターン応募数4倍増
三井住友銀行は、新卒採用の早期化に対応し、従来は3年生4月だった採用イベント参加を2年生向けの2月へ前倒ししました。就職活動への意識が高い層に早期に情報を届ける狙いです。
イベント参加回数は前年比約30%増となり、就職ナビの先行掲載やWebセミナー活用も強化してオンライン接点を広げました。
その結果、サマーインターン応募数は前年比4倍に増加しました。採用ブランディングでは、何を伝えるかに加え、いつ始めるかの設計が成果に直結します。
ダイキン工業|採用メディア刷新と動画活用で第一志望志向を高めた
ダイキン工業は、同業他社との競合下で第一志望層の獲得に課題があったため、採用ブランディングの一環として採用サイトを全面刷新しました。
“働く理由”や“挑戦ストーリー”を軸に構成し、求める人物像と働き方を明確に打ち出しています。トップページには採用コンセプト「100→0の人材」を説明する動画を掲載し、文字情報に抵抗がある世代にも思いを直感的に伝えられる設計にしました。
さらに「働く仲間」コンテンツで社員や内定者の声を発信し、ソーシャルリスニングで反響を分析するとともに、外部メディアのインタビュー露出も組み合わせています。
これらの施策により、候補者のブランド理解が深まり、第一志望としての志向を高める効果が表れています。
【IT・スタートアップ】採用ブランディングの成功事例

IT・スタートアップ企業は、スピード感と柔軟性を武器に優秀な人材確保を進めています。事業の急成長や社内文化の変化が早く、求職者に安定感や将来像を伝えにくい課題も抱えがちです。
ここでは、IT・スタートアップ企業の採用ブランディングの成功事例を紹介します。
サイバーエージェント|「本当の姿」を発信しリアルな働き方を伝達
サイバーエージェントは、採用ブランディングの精度を高めるため、応募者ヒアリングに加えて志望度に左右されない学生アンケートを導入し、自社の採用ポジションを客観的に把握しました。
リサーチ結果は「広報」「選考体験」「クロージング」の三段階に整理し、候補者が重視する情報を各段階で一貫して届ける設計にしています。
さらに、成長環境や多様性、事業規模といったキーメッセージを最適なタイミングで発信することで、ブランドの理解を深め、意思決定を後押ししました。
これらの取り組みにより、エントリー数は2年間で約2倍へと伸長し、事実に基づく情報設計で「本当の姿」を伝えることが、リアルな働き方の訴求と成果につながることを示しています。
サイボウズ|働くママ応援施策で離職率を28%→4%に改善
サイボウズは、Officeやkintoneなどのグループウェアを展開し、採用ブランディングでは「働くママ応援」に焦点を当てて共感型の発信を強化しています。
育児と仕事を両立する社員の姿を描いたムービーを、テレビやネットで公開し、YouTubeでは広告なしで162万回超の再生を獲得しました。
また、子連れ出社・リモート・フレックスなど多様な働き方を明確に打ち出した結果、離職率は28%から4%へ大幅に改善しています。
GA technologies|ビジュアルアイデンティティ導入で新卒採用を強化
GA technologiesは不動産DXを手がけ、採用ブランディングの一環として新卒市場での認知拡大に注力しています。経験者中心だった体制を見直し、自社の価値やビジョンを視覚化するVI(ビジュアルアイデンティティ)を策定しました。
これを基軸に採用サイトをリニューアルし、未経験者にも伝わりやすいデザインと言葉で魅力を発信しています。合同説明会や採用イベントでは、VIを配したクリアファイルやTシャツを配布して記憶に残る接点を増やしました。
その結果、サイト訪問数は約2.5倍、新卒エントリー数は約2倍へと伸長しています。
さらに、カルチャーや働く環境を伝えるオウンドメディア運用を通じて、社員インタビューやプロジェクト紹介を継続的に発信し、入社後のミスマッチを抑えながら適した人材の獲得につなげています。
こうした一貫したビジュアルとメッセージの設計により、同社は新卒採用の強化とブランド力の向上を同時に実現しています。
コインチェック|カルチャーブック作成で理念共有とブランド力を向上
コインチェックは、採用ブランディングの一環として企業理念と価値観をまとめた『カルチャーブック』を制作し、理念共有とブランド力の向上を図っています。色味や紙質まで設計意図を反映させ、手に取った瞬間に世界観を体験できるようにしました。
求職者へ配布することで、入社前から企業文化を直感的に理解でき、応募意欲が高まりやすい状態をつくっています。また、社内でも同冊を共通テキストとして運用し、考え方や行動指針をそろえることで、部署をまたいだメッセージの一貫性を強めています。
こうした取り組みにより、応募数の増加やミスマッチの低減といった採用効率の改善につながり、社内外で同社のブランド理解が深まっています。
クリエイティブテックスタジオ|SES業界の懸念を打ち消し応募数を増加
クリエイティブテックスタジオは、採用ブランディングの一環としてエンジニアのキャリアパスを明確化し、SES業界への不安を解消する情報設計を進めています。
採用LPでは「PMへの道筋」や「高還元・質の高い案件」を具体的に示し、事業紹介と代表メッセージで自社の強みを伝えます。
募集要項には年収レンジ・必須スキル・アサイン事例を明記し、LP下部に応募フォームを配置して、興味喚起から応募までの導線をシームレスに整えています。
これらの取り組みにより、候補者の懸念が和らぎ、応募数が大幅に増加しました。同時にミスマッチの防止にもつながり、質の高い人材獲得と採用ブランディングの強化を実現しています。
【地方・中小企業】採用ブランディングの成功事例

地方・中小企業では、限られた予算や知名度の中で、自社ならではの魅力をいかに伝えるかが採用ブランディング成功のカギとなります。ここでは、地方・中小企業の採用ブランディングの成功事例を紹介します。
三幸製菓|採用コンセプト刷新で新卒エントリー数を300名→13,000名に拡大
三幸製菓は、採用ブランディングを軸に採用コンセプトを刷新し、認知不足の課題に正面から取り組みました。
ブランド調査で自社認知度が約20%と判明したことを受け「熱量と成長力をもった知られざるお菓子メーカー」をコアメッセージに設定し、採用サイトとパンフレットを赤基調で統一しました。
さらに、巻物型パンフレットを導入して記憶に残る体験を設計し、合同説明会では成長スピードを数字とエピソードで力強く訴求しています。
こうした一貫したブランディング施策により、約3年で新卒エントリー数は300名から13,000名へと大きく伸び、同社の魅力が候補者に伝わる設計へと進化しました。
アンビスホールディングス|LINE応募導入で応募者増加と接点拡大を実現
アンビスホールディングスは、慢性期・終末期に特化したホスピス「医心館」を中心に医療・介護サービスを展開し、採用ブランディングを強化しています。
社員の仕事や日常の“素顔”を伝える記事を定期的に発信し、堅苦しさを抑えたタイトルで親しみやすさを高める設計にしました。これにより応募者が増え、面接数も着実に伸びています。
さらに、応募窓口にLINEを導入し、メールや紙より手間を抑えてワンタップで応募できる導線を整えました。
公式LINEでは社風や業務内容を継続的に発信し、応募前後における情報提供とコミュニケーションの機会を拡大しています。こうしたメッセージと導線の両輪により、同社は候補者との接点を広げつつ、応募転換の効率も高めています。
ユニファ|理念共有とインナーブランディングで社員数を20名→220名に拡大
ユニファは保育施設向けICT「ルクミー」を展開し、2017年から採用ブランディングに本格着手しました。開始当初は、企業理念や社会課題への貢献意欲が応募時に十分伝わらず、ミスマッチが課題でした。
そこで、求人サイトで理念を前面に出した記事を継続発信し、人事と広報が連携して最新の採用記事を更新しました。社内向けにはワークショップや事例共有を行い、理念への共感を育むインナーブランディングを強化しました。
こうした外向けの情報発信と内向けの浸透施策を両輪で進めた結果、社内外で理念理解が深まり、定着率とエンゲージメントが向上しました。その積み上げにより、同社は数年で社員数を20名から220名へと拡大し、理念起点の採用活動を持続的な成長につなげています。
八百鮮|SNS活用とビジュアル刷新で求職者数を5倍に増加
八百鮮は全国でスーパーマーケットを展開し、採用ブランディングを強化しています。まず、採用サイトを刷新して“八百屋らしからぬ”洗練されたビジュアルに統一し、動画やパンフレットで職場のリアルを伝えました。
さらに、InstagramやXなどのSNSで狙う層へ直接アプローチし、接点を拡大しました。これらの取り組みにより、求職者数は従来比で5倍に増え、仕入れ担当など重要ポジションにも適材を獲得できています。
デジタルメディアの活用とブランド刷新を両立させ、人材確保と事業成長の両面で成果を上げています。
ワンコイングリッシュ|ファン獲得型採用で離職率を低下し長期的な人材確保に成功
ワンコイングリッシュは、採用ブランディングで「短期の人数確保」よりも、応募者をファンに育てる長期戦略を重視しています。
500円で英会話を提供する強みを土台に、社内のアットホームさや働きやすさをSNSと採用ページで継続発信し、応募者に寄り添うコミュニケーションを徹底しました。
また、定期的な社員インタビューで入社後の姿を具体的に示し、期待と実態のギャップを小さくしています。こうした取り組みにより、入社後のミスマッチが減少し、離職率は業界平均を大きく下回る水準まで改善しました。
結果として、質の高い人材を安定的に確保できる体制が整い、既存社員や受講生からの紹介による応募も増えるなど、持続的な人材プールの形成につながっています。
採用ブランディングにおける失敗事例

採用ブランディングには、成功事例から得られるノウハウも多いですが、その裏では思わぬつまずきも見受けられます。ここでは、採用ブランディングにおける失敗事例を紹介します。
イメージ重視で現場との乖離が生じたケース
採用ブランディングで見た目や好印象づくりを優先しすぎると、入社後のミスマッチと早期離職を招きます。候補者は「入社後の自分」を想像して応募するため、実態とかけ離れた発信は期待とのギャップを生みやすいからです。
例えば、体力を要する屋外・工場作業が中心の企業が本社オフィスで撮影した写真を採用媒体に多用し、説明会でも給与・福利厚生を前面に出した場合、応募数と採用数はいったん増えます。
しかし、配属後に「想像と違う」「続けられない」という声が相次ぐと、実務と訴求イメージの乖離を原因とした早期離職が増加するでしょう。
現場の厳しさや安全基準、必要な体力・姿勢を明示しつつ、やりがいや成長機会を現場社員の声や動画で具体的に伝えると、期待値のギャップを縮められます。
また、職場見学・業務同伴・短時間体験などのリアル体験や適性セルフチェックを導入すると、応募前の自己選択が進み、定着率の改善につながります。
上層部主導で社員の共感を得られなかったケース
採用ブランディングをトップダウンで決めると、現場の納得感を得られず、運用段階でメッセージが機能しなくなります。理念は「現場の言葉」で語れてはじめて、候補者体験に一貫性が生まれます。
例えば、部門長会議で方針を決め、人事主導で理念と行動規範を軸にしたメッセージを策定し、ホームページやポスターなどのツールを一斉に整備して社内展開した場合です。
共有後に「理想論が先行している」「現実が伝わらない」といった声が相次ぐと、現場の共感を得られないことがあります。施策をそのまま進めると、発信と実態のズレが拡大し、応募と定着の双方に悪影響が及びます。
検討初期から現場社員を巻き込み、具体的な業務事例や価値提供の実感をメッセージへ織り込むと、運用時の腹落ちが高まります。
また、社内ワークショップや部門横断レビューで合意形成を進め、ガイドラインやFAQを整備します。四半期ごとにフィードバックを回収して改訂を重ねれば、内外の一貫性が高まり、共感に基づく運用へ移行できます。
ダイバーシティ訴求が環境整備に追いつかなかったケース
採用ブランディングで多様性を強く打ち出しても、受け入れ体制が伴わなければ入社後の不信や早期離職につながります。候補者は発信内容を「約束」として受け取るため、実態とのギャップが信頼を損ないやすいからです。
例えば「営業職で女性を積極採用する」と掲げ、活躍事例や産育休支援をHPや就職ナビで大きく紹介した場合、応募は増え、狙い通り女性人材を採用できます。
しかし、入社後女性営業が実質1名で産育休の運用実績も乏しい現場であれば、発信と現実の乖離から不安が高まり、早期離職のリスクが生じます。この場合、受け入れ環境の整備と情報開示を並走させることで期待値のギャップを抑えられるでしょう。
配属先のメンター配置や女性管理職の増員計画、制度の運用実績と今後の目標値の公開、現場の声を含むQ&Aの提示を進め、進行中の取り組みは段階と期限を明示して更新情報を継続発信します。これにより、候補者との認識を適切に揃えることが可能です。
縁達磨では縁起こしブランディングで商売繁盛を支援
縁達磨では「縁起こしブランディング」で採用ブランディングを支援いたします。
候補者が「この会社で働きたい」と思う理由を言語化し、応募から入社・定着まで一貫した体験として届けることを目的としています。理念や価値観を採用の文脈に落とし込み、現場の声で裏づけながら、共感が生まれるメッセージと判断基準を整えます。
「どこから手を付ければよいか分からない」という段階でも問題ありません。課題の整理から社内の合意形成、実行と改善までを一気通貫で支え、持続的に選ばれる採用の基盤をつくります。
商売のお悩みはいつでもご相談ください
この記事では、大手企業からIT・スタートアップ、地方中小企業まで、採用ブランディングの成功・失敗事例を幅広くご紹介しました。事例から見える共通点を手がかりに、自社の規模や課題に合う施策へと落とし込んでみてください。
縁達磨の「心・敵・技・体・動」5工程による縁起こしブランディングは、販売力強化と未来の競争力構築を両立する独自手法です。商売繁盛を目指すお悩みやご相談は、いつでもお気軽にお声がけください。
お問い合わせはこちら : お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら : お気軽にお問い合わせください。
Drop us a line.