
2025.10.24
【業種別】企業ブランディングの成功事例15選!注意点も紹介
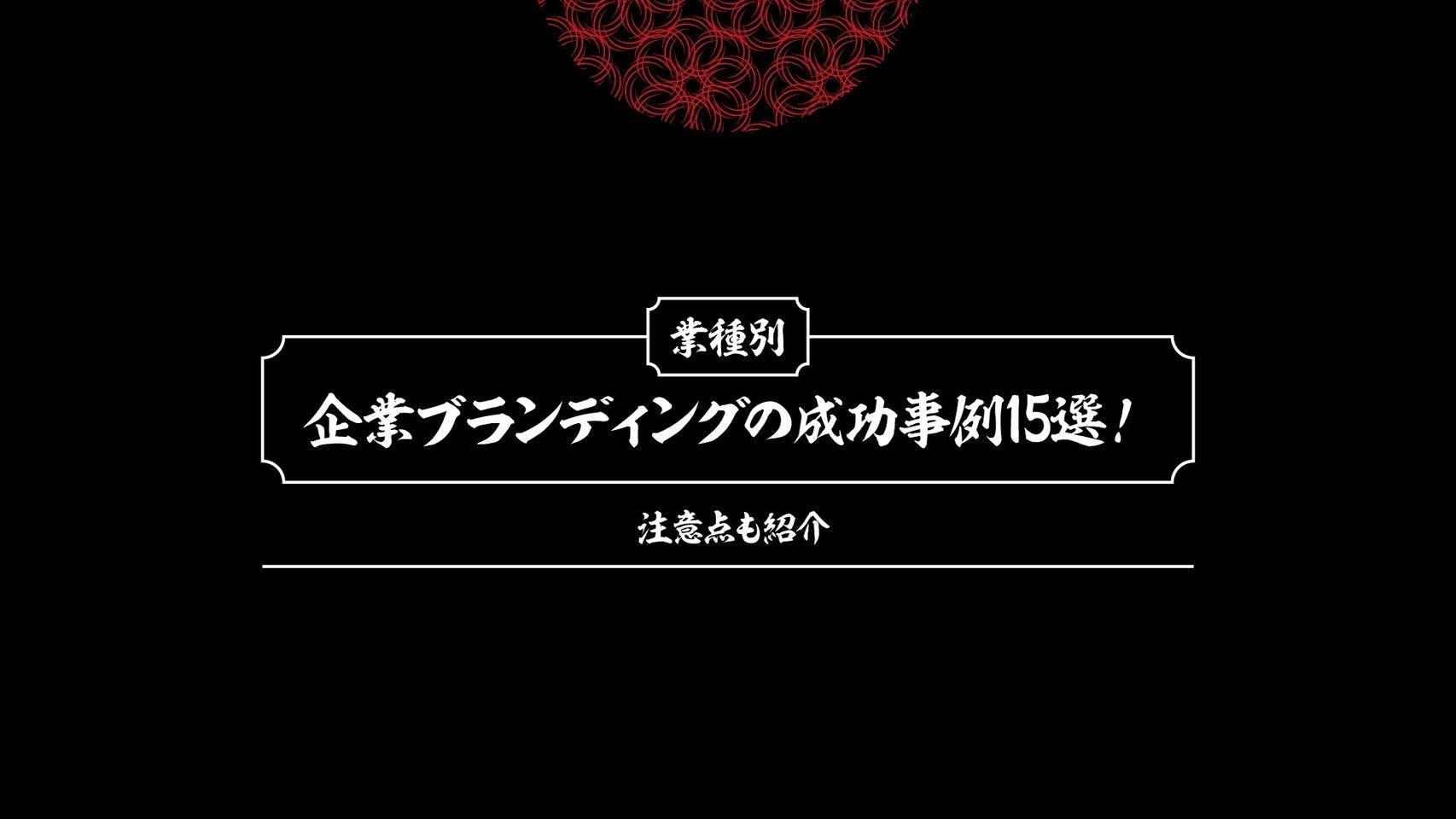
市場競争が激しくなる中「自社の強みをどう伝えるか」「選ばれる理由をどう築くか」は多くの企業が抱える課題です。中でも成果を上げている企業は、戦略的な“企業ブランディング”によって価値を明確に打ち出しています。
本記事では、小売・アパレル、食品・飲料、住宅・製造など業種別に、企業ブランディングの成功事例を15社紹介するとともに、取り組む際の注意点を解説します。
【小売・アパレル】企業ブランディングの成功事例

小売・アパレル業界は、顧客の日常生活に密接に関わるだけに「ブランドとしての世界観」や「店舗での体験価値」がそのまま売上やリピート率に直結します。ここでは、小売・アパレル業界の企業ブランディングの成功事例を紹介します。
ユニクロ|グローバルアパレルブランドとして確立
ユニクロは、シンプルで高品質な日常着を提供する「LifeWear」コンセプトを掲げ、世界中で支持を集めています。特に、独自開発のヒートテックやエアリズムは、東レとの技術協業により生まれ、機能性と快適性を兼ね備えています。
また、兵庫県のカイハラデニムや熟練の職人による縫製技術を取り入れ、伝統的な技術と現代的なデザインを融合させています。さらに、リサイクル活動や障がい者雇用、難民支援などの社会貢献活動を積極的に行い、企業の社会的責任を果たしています。
これらの取り組みにより、ユニクロはグローバルなアパレルブランドとして確立し、持続可能な社会の実現に向けて挑戦し続けています。
無印良品|世界的ライフスタイルブランドへの成長
無印良品は、1980年の誕生以来、「必要なものを必要なだけ」というシンプルなコンセプトを軸に、無駄をそぎ落とす“引き算の美学”を徹底しています。
素材や製造工程の透明化、白を基調としたミニマルな店舗やパッケージ、一貫したブランド表現で誠実さを伝える設計が特徴です。 また、再生可能素材の活用や地域文化を取り入れた「Found MUJI」による製品開発、長く使えるデザイン推進など、サステナビリティを重視した取り組みを展開しています。
これらの姿勢が、日本発の世界的ライフスタイルブランドへの飛躍を支えています。
さらに、無印良品は「これでいい」というブランドコンセプトを掲げ、過剰な装飾や加工を廃したシンプルで自然なデザインの商品を提供しています。この価値観は、深く社会に浸透し、消費者の心を捉えています。
資生堂|日本発プレミアムブランドの確立
資生堂は1872年創業の日本発プレミアムブランドです。日本の美意識と先端科学を融合した独自性を軸に、R&D拠点「グローバルイノベーションセンター」で技術を磨き、1916年創設の資生堂ギャラリーや美術性の高いパッケージで文化価値を発信してきました。
世界120超の国・地域でも、日本らしさを守りつつ各地の肌質や価値観に合わせて製品とコミュニケーションを最適化します。こうした一貫した企業ブランディングを社会貢献や環境配慮と結びつけ、同社は「美の創造企業」という地位を国際市場で確立しています。
【食品・飲料】企業ブランディングの成功事例

食品・飲料業界でのブランディングは、原材料の産地や製造工程、味わいの独自性をいかに消費者に伝えるかが勝敗を分けます。ここでは、食品・飲料業界の企業ブランディングの成功事例を紹介します。
湖池屋|老舗ブランドの刷新と再評価
湖池屋は老舗ブランドの刷新を目的に、企業ブランディングを推進しました。老舗の料亭を想起させる世界観を掲げ、六角形の新ロゴに「湖」を配して家紋風に表現し、「親しみ・安心・楽しさ・本格・健康・社会貢献」の六つの価値を示しています。
創業者の手揚げのこだわりも可視化し、2017年には国産じゃがいも100%の「KOIKEYA PRIDE POTATO」を白基調で発売しました。
SNSで話題となり年間売上40億円を達成し、グッドデザイン賞も受賞しました。伝統を生かして新たな価値を重ね、老舗ブランドの刷新と再評価を実現しています。
KOYASU FARM|地域ブランド化による販路拡大
KOYASU FARMは、福岡県宇美町の由来「産み」とヤギミルクの歴史を結びつける企業ブランディングで、地域ブランド化を進めています。商工会の専門家派遣とクラウドファンディングで資金を整え、2018年秋にヤギミルクアイス「うみあいす」を開発しました。
移動販売車や常設店、地域イベントでの展開によって認知を広げ、ビジネスプランコンテスト大賞を機に百貨店へ販路を拡張しています。
さらに、商品名を「産み愛す」へ改め、福岡デザインアワード銀賞と六次化商品コンクール審査委員特別賞を受け、ブランド価値を高めることで販路拡大に弾みをつけています。
やぶうち商会|自然派化粧品ブランドの確立
やぶうち商会は、塗料卸に加えてトウキ葉を活用した化粧品事業へ参入し、企業ブランディングを「自然派×地域資源」に定めて展開しています。
自社ブランド「LALAHONEY」では、トウキ葉エキスを主成分とするスキンケアを商品化し、地元産の安心感と抗酸化作用の科学的裏付けを組み合わせて信頼性を高めました。
オンライン直販に加えて百貨店やアジア向け輸出を開拓し、販路を広げています。さらに、地元農家との連携やリサイクル可能素材の採用によって、地域貢献と環境配慮を両立させています。
これらの取り組みにより、同社は自然派化粧品市場での地位を着実に確立し、持続可能なブランドとして評価を高めています。
とらや|伝統と高級感のブランド強化
とらやは創業400年以上の老舗和菓子店として、厳選素材と職人技の一貫生産で上質な羊羹や季節菓子を提供し、高級感のある企業ブランディングを強化しています。
経営理念「おいしい和菓子を喜んで召し上がっていただく」を軸に、パッケージや店舗へ季節感と自然美を取り入れ、直営店の空間演出とオンライン刷新で富裕層の支持を広げています。
さらに、海外百貨店での展開やコラボ、デジタル施策にも注力し、伝統技術を継承しながら現代的なデザインを採用することで若年層にも届くブランドへ進化させています。
【住宅・建設・インフラ】企業ブランディングの成功事例

住宅・建設・インフラ業界は、住まいや社会インフラに直結するため、信頼性と品質がブランド価値の礎となります。ここでは、住宅・建設・インフラ業界の企業ブランディングの成功事例を紹介します。
日本鋳鉄管|理念を伝えるコーポレートブランドへ
日本鋳鉄管株式会社は、水道・排水用鋳鉄管を扱う老舗企業ですが、市場縮小とステークホルダーとの接点不足により事業価値が伝わりにくい課題を抱えていました。
そこで、企業ブランディングの観点から、時代を超えて通用する未来志向かつ厳格さを備えたコーポレートロゴへ刷新し、さらにミッション・ビジョンを明示したWebサイトへリニューアルしました。
これにより理念が社員と顧客に浸透し、企業価値を見える化できました。結果として信頼性が高まり、顧客や地域とのコミュニケーションが活性化し、持続可能な成長基盤を強化しています。
大和ハウス工業|ブランドポジションの明確化
大和ハウス工業は、住宅・建設・不動産分野の大手として、企業ブランディングの観点からブランドポジションの明確化に取り組んでいます。
市場調査でターゲットを絞り、想定顧客像と競合状況を整理したうえで、企業理念を体現するタグラインやキャッチコピーを策定し、思想を実装するための中心要素を体系化しています。
さらに、顧客接点となるビジュアルデザインを磨き直し、意図するブランドイメージを反映したWebサイトへ刷新することで、一貫性と魅力を両立したブランド体験を提供し、顧客との信頼関係を強めています。
また、「建築の工業化」を掲げる企業姿勢のもと、プレハブ住宅のパイオニアとして先進技術を進化させ、多様な住まい方やニーズに応える商品・サービスの提供体制を整えています。
【製造業】企業ブランディングの成功事例

製造業は、品質や技術力を軸としたブランド構築が求められる領域です。機能性だけでなく、顧客の心に届くストーリーやデザイン、サステナビリティを訴求する施策が不可欠です。
ここでは、製造業の企業ブランディングの成功事例を紹介します。
中村ブレイス|ニッチ市場での圧倒的ブランド力
中村ブレイスは島根県本社の医療用品メーカーとして、義肢装具や医療用ウィッグなど専門性の高い製品でニッチ市場に挑み、卓越した技術力と品質で業界内のブランド力を高めています。
特に、顔面補綴や乳房補整具では、患者ごとの状況に合わせてオーダーメイド製作を徹底し、職人精神に基づく精緻な“Made in Japan”の仕上がりで、米国やアジアの医療機関から高い評価を得ています。
創業者が掲げた患者中心主義を受け継ぎ、使用者のQOL向上を最優先に開発を行う姿勢が、技術と哲学の一貫性を生み、企業ブランディングの核として機能しています。
結果として「特定の小市場で一番を目指す」集中戦略を実務で体現し、競争が限られる領域で安定した収益と揺るぎないブランドポジションを確立しています。
テオリアホールディングス|美容領域での独自ポジション確立
テオリアホールディングスは「美容は生き方」という企業ブランディングを掲げ、ベルタとナビジョンで独自のブランド体験を提供しています。
妊娠中・産後女性向けのベルタでは、ライフステージに寄り添う製品と共感メッセージを軸に、熱量の高いファンづくりを進めています。
公式ブログやSNSなどのオウンドメディアでは、美容・健康情報を継続発信し「ベルタスタイル」で妊娠・育児の悩みに具体的に応えることで、化粧品を超えたパートナーとしての信頼を高めています。
さらに、医学的アプローチのナビジョンと自然由来のベルタという異なる個性を「本質的な美」という共通理念で束ね、自社研究所と専門家連携による開発体制を整えています。
これらの取り組みにより、競争が激しい美容市場においても、一貫性のある価値提案で独自のポジションを確立しています。
バーミキュラ|高価格帯でも選ばれるブランドへ
バーミキュラは、愛知ドビーが2010年に発売したホーロー鍋で、3万円という高価格帯にもかかわらず累計30万台を販売しています。
ステンレスと鋳物ホーローの長所を融合した高気密設計により無水調理を可能にし、失敗作1万個と3年以上の試作を重ねた技術力が品質への信頼を高めました。
さらに「暮らしをかえる鍋」という明確なブランドメッセージを軸に、食卓や健康、家族の会話まで変わる体験価値を訴求する企業ブランディングを展開しています。
購入後は専用コールセンターや専属シェフによるレシピ提案で顧客の声に応え、製品・言葉・サービスを一貫させる運用体制を整えました。こうした技術と体験の両輪により、同社は高価格帯でも選ばれ続けるブランドへと成長しています。
近畿編針|グローバル展開で売上拡大
近畿編針株式会社は、海外で自社ブランドの伸び悩みを受け、企業ブランディングの観点からグローバル向け新ブランドを立ち上げました。全社員でブランドコンセプトを検討し、同社の技術力と歴史を反映した言葉へ落とし込むことで、発信の軸を明確にしました。
ネーミングとロゴは英語圏でも直感的に伝わる表現を採用し、デザイナーと連携してECサイト用ビジュアルやプロモーション素材まで一体で刷新しました。
こうした一貫したブランド設計と表現の統一により、欧米・アジアでの認知度が大きく高まり、売上の大幅な増加につながっています。結果として、自社ブランドの競争力を強化し、新規取引先の獲得も進んでいます。
マウンテンディアー|地域産業の復活
マウンテンディアーは、Uターンした山鹿社長がデザイナーの妻と太田市で起業し、衰退していた地元ニット産業の再生を目指して2017年に「OTA KNIT」を立ち上げました。
工場が生産、同社が企画・マーケティングを担う体制で企業ブランディングを進め、グッドデザインぐんま優秀賞の受賞や、商工会支援によるギフトショー出展・著名アーティストとの協業につなげています。
さらに2021年には新ブランド「Mebuki」を始動し、クラウドファンディングで305万円を調達して若年層の認知を高めました。地元工場との連携から派生したファクトリーブランドも増え、70年続くニット産業を次世代へつなぐ基盤を着実に強化しています。
マストロ・ジェッペット|伝統産業の再生と海外展開
マストロ・ジェッペットは、南会津町の伝統木工業者と外部デザイナーが協業して設立され、企業ブランディングの観点から国産木製玩具の再評価に取り組んでいます。
伝統技術を土台に「木の温もり」「安心して遊べる頑丈さ」「洗練されたデザイン」を核とし、木材選定から設計・加工までは地域企業が担い、イタリア人デザイナーが世界観を統一しています。
欧州の玩具見本市では、日本製ならではの精密設計と安全性が高く評価され、認知が大きく高まりました。
これを機に国内外の販路が拡大し、確固たるブランドを築くことができました。地域の伝統産業を未来へつなぎながら、同社はさらなる海外展開にも意欲的に取り組んでいます。
企業ブランディングに取り組む際の注意点
企業ブランディングで重要なのは、ブランドストーリーや価値観を明確にし、一貫性を保つことです。しかし、計画段階でターゲットを誤ったり、短期的成果ばかりを追うと、本来の目的から逸脱する恐れがあります。
ここでは、企業ブランディングに取り組む際の注意点を紹介します。
ターゲット分析を怠らないようにする
企業ブランディングを成功させるには「誰に向けてメッセージを届けるのか」を明確にすることが不可欠です。ターゲット像が曖昧なまま施策を進めると、訴求内容がぼやけ、誰にも刺さらない発信になってしまいます。
そのため、年齢・性別・価値観・職業・行動パターンなどを踏まえ、具体的なペルソナを設定することが重要です。SNSのコメント分析やアンケート調査を通じてニーズを把握し、生活スタイルや情報接触の傾向を整理します。
例えば、20代の女性を主なターゲットとする場合は、SNSや動画を中心に「共感」や「世界観」を重視した発信が効果的です。一方、40代以上のビジネス層であれば、信頼性や実績を伝えるコンテンツのほうが響きやすい傾向にあります。
このように、ターゲット分析を徹底することで、より効果的かつ一貫したブランディング戦略を構築できます。
短期的な成果だけを追い求めないようにする
企業ブランディングでは、短期の数値だけに偏らず、長期視点で価値を積み上げることが不可欠です。単発のキャンペーンで一時的に話題化しても、想起や信頼の定着にはつながりにくいためです。
ブランドは、約束した価値を一貫して届け続ける体験の蓄積で強くなります。短期成果のみを追うとメッセージがぶれ、顧客との関係が細り、将来の成長余地を自ら削ってしまいます。
そこで、売上やCVRなどの短期指標に加え、顧客満足度・NPS・リピート率、指名検索数、口コミ量、従業員エンゲージメントなどの中長期KPIも設定します。バランスト・スコアカード(BSC)を用い、財務・顧客・内部プロセス・学習と成長の各観点で目標と施策を連動させます。
四半期ごとに発信内容と候補者・顧客接点の品質をレビューし、アンケートやSNSの反応を踏まえて改善を重ねます。こうした多角的な評価と継続的な改善により、短期成果を確保しながら、持続的なブランド価値の向上を実現できます。
社内での情報共有不足に気をつける
企業ブランディングを成功させるには、部門をまたいで情報を共有し、同じメッセージで動ける状態をつくることが不可欠です。共有が不足すると解釈や表現がばらつき、せっかくの施策が相殺されてしまいます。
そのため、ブランド理念・価値観・最新施策を共通言語にする場を設け、日々の業務に落とし込むことが重要です。社内研修やワークショップで合意を形成し、ガイドラインやFAQを整備して迷いを減らします。
例えば、社内SNSやナレッジベースで進捗と成功事例を定期的に公開し、部門横断ミーティングで課題を早期に共有します。メールだけに依存せず、誰もが見える場所で情報を更新することで滞留を防ぎ、連携のスピードと一貫性を高められます。
このように、見える化と定期共有を徹底することで、全社一体の運用が実現し、ブランド価値を継続的に高める基盤を築けます。
縁達磨では縁起こしブランディングで商売繁盛を支援
縁達磨は、企業が長く選ばれ続けるための基盤づくりを支援し、方針設計から実装・検証・改善まで一貫して伴走します。
理念や価値観を丁寧に見直して本来の強みを言語化し、社会や顧客に一貫して伝わるよう整えることで、短期の手応えと中長期の価値向上の両立を目指します。
また、指名検索、再購入、商談化率といった「選ばれ続けているか」を示す指標を重視し、継続的に検証します。企業ブランディングの具体化に取り組みたい方は、現状整理の段階からお気軽にご相談ください。
商売のお悩みはいつでもご相談ください
本記事では、小売・アパレルから製造業、住宅・食品産業まで計15社の成功事例をもとに、企業規模や業種ごとのブランド構築ポイントと注意点を解説しました。
失敗を避けるには、ターゲット分析や社内共有、中長期的視点での取り組みも欠かせません。ブランド強化には、想いの言語化や競合環境の徹底分析、組織体制の整備、そして継続的なPDCAが必要です。
縁達磨の縁起こしブランディングは、短期間で売上アップと顧客満足度向上を実現します。
商売のお悩みやブランド戦略の再構築など、いつでもお気軽にご相談ください。経験豊富な専門チームが、御社の次なる飛躍を全力でサポートいたします。
お問い合わせはこちら : お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら : お気軽にお問い合わせください。
Drop us a line.