
2025.09.28
MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)とは?意味をわかりやすく紹介
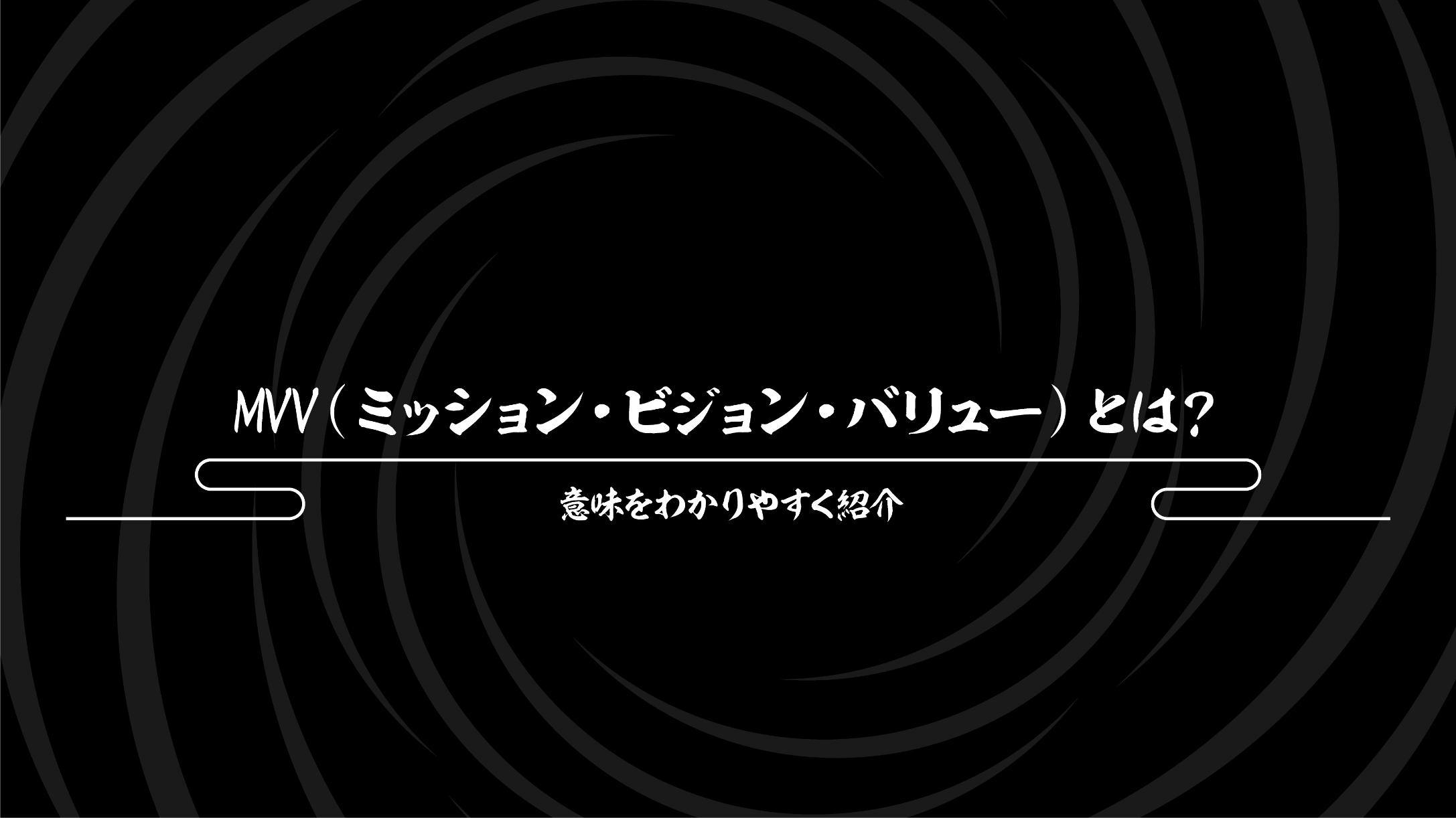
企業活動を進めるうえで欠かせない「MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)」。しかし「企業理念や経営理念と何が違うの?」「なぜ必要なの?」と疑問を持つ方も少なくありません。
本記事では、MVVの基本的な意味や他の理念との違い、策定することで得られる効果などをわかりやすく紹介します。
MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)とは

MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)とは、企業の「存在意義や活動指針、価値観」を指します。
ミッションとは、企業の存在意義のことで「何のためにこの会社は存在しているのか?」という問いへの回答になります。近年では「解決したい社会課題を指していることが多い」と言われています。
ビジョンとは、ミッションを実現するために、企業が長期的に成し遂げようとする理想の姿のことです。ビジョンは単に理想像を示すだけでなく、実現に向けた道筋(=戦略性)を含んでいる点を考慮する必要があります。
バリューとは、ビジョンを実現するために社員一人ひとりが日々の意思決定をする際、常に考慮すべき価値観・判断基準のことを指します。バリューは複数設定されることが多く、3〜5個程度が理想とされています。
MVVと「企業理念」「経営理念」などとの違い
MVVは、企業が目指す方向性を明確にするためのフレームワークです。
- ミッション(Mission)...... 企業が社会で実現したいこと
- ビジョン(Vision)......ミッションが実現したときの理想の姿
- バリュー(Value)......大切にする価値観や行動指針
一方、企業理念は法人格を持つ企業の存在意義を示すものであり、「企業が存在する目的や意義」と定義されます。設立当初から存在し、経営理念や運営指針を包括する上位概念として位置づけられるのが一般的です。
経営理念は、企業が経営活動を行ううえで重視する価値観や信念を示すものであり、「企業が存在意義を達成するために守るべき価値観や信念」と定義されます。企業理念の下位に置かれることが多い点が特徴です。
また、経営理念が強固であるほど、ミッションやビジョンといったMVVの各要素は、その価値観に沿って調整される傾向があります。
MVVの重要性

MVVは、社内の意思統一と社外への一貫した発信を実現するために重要です。
社内においては、存在意義や価値観を明文化することで、経営陣から従業員まで共通認識を持てるようになり、以下の判断や設定がぶれにくくなります。
- 経営判断
- 目標設定
- 方針策定
同じ企業文化を共有することで、従業員のエンゲージメントが高まり、組織の一体感も強まります。
社外においては、MVVが投資家・求職者・顧客といったステークホルダーに対する「企業のアイデンティティの表明」となります。IR活動や採用広報において、自社の思想や方向性を明確に伝える指針となり、信頼の獲得や共感の醸成につながります。
MVVを策定することで得られる効果

MVVを策定することは、企業活動を進める上で非常に重要です。ここでは、MVVを策定することで得られる4つの効果について紹介します。
従業員の意欲を高められ、離職を防止できる
MVVを策定すると、従業員の意欲を高め、離職を防止する効果が期待できます。
ミッションは社員一人ひとりの意思決定の指針となり、ビジョンは理想的な姿を示します。バリュー(価値観)は、日々の業務で大切にすべき基準として意識されます。
これらを明文化することで、社内で暗黙の了解とされてきた価値観を明確化できます。その結果、社内文化の醸成が加速し、組織全体の結束力が強まります。
結束力と共通認識が高まることで、従業員は安心して働けるようになり、働きがいの向上が離職防止へとつながります。
理念に共感する人材を採用できる
MVVを策定すると、理念に共感する人材を採用しやすくなり、入社後のミスマッチを防げるため、定着率やパフォーマンスの向上につながります。
近年の入社先を決める際に重視されるのが、企業のビジョンやミッションです。そのため、MVVを明確に打ち出して発信できる企業は、理念に共感する人材を惹きつけやすくなります。
発信内容に一貫性を持たせられる
MVVを定めることで、会社としての発信内容を常にぶれさせずに保つことができます。
例えば、自社のバリューを社員表彰の基準に取り入れたり、日々のコミュニケーションの指針としたりする企業が増えています。こうした運用を続けることで、社員一人ひとりが同じ価値観をもとに行動し、外部への発信も統一感のあるものになります。
また、広報やマーケティング活動においても、MVVを基盤にしていれば「会社として何を大事にしているのか」を一貫して伝えられます。市場環境や技術が変わって事業の方向性を見直す場面があっても、ミッションやバリューを軸にすれば、自社らしさを失わず安定したメッセージ発信が可能です。
情報共有が円滑になり、意思決定がスムーズになる
MVVを策定することで、社内の情報共有がスムーズになり、意思決定のスピードも高まります。
マネージャーや現場がそれぞれ異なる方向性で判断していては、意思疎通に齟齬が生じ、混乱を招いてしまいます。MVVが共通の指針となることで、組織全体で目的を共有し、迷いなく意思決定を進められます。
MVVの策定はいつ行うべきか?

MVVは会社や組織の「軸」となる考え方です。本来は、起業したときや新しいブランドを立ち上げる際に策定するのが理想です。
ただし、一度作ったら終わりではなく、社会の変化や会社の方向性に合わせることも大切です。
例えば、 下記のようなときには「何を大事にして事業を進めるのか」という価値観を改めて確認し直す必要があります。
- 事業が成長して競争が激しくなったとき
- 新しい市場に挑戦するとき
また、下記のような会社の節目も、MVVを見直す良いタイミングです。
- 社長が代わったとき
- M&Aで会社の体制が変わったとき
- 周年記念の節目
- 上場のとき
MVVを策定するための3つのステップ

MVVを策定・再策定する際には、ただ理念を掲げるだけでは不十分です。実際の事業戦略や組織の意思決定に落とし込めるよう、経営層自身がまず事業内容を明確化することが重要です。
ここでは、MVVを策定するための3つのステップを紹介します。
経営層で事業内容を明確化する
MVVを策定する最初のステップは、経営層が事業内容を整理することです。MVVは企業の根幹に関わるため、代表や経営幹部、役員層など、事業理解の深いメンバーが中心となることが重要です。
事業内容を明確にすれば、市場や顧客のターゲットがはっきりし、戦略の方向性がぶれにくくなります。
具体的な進め方としては、下記の方法があります。
- 代表・経営陣などキーパーソンへのヒアリング
- 経営メンバーによるセッション
このプロセスを徹底することで、MVVの土台となる「在りたい姿(ビジョン)」や「大切にすべき価値観(バリュー)」が浮かびやすくなります。
顧客・競合・自社を分析する(3C分析)
次に、3C分析を行います。顧客・競合・自社を多角的に分析すれば、業界内でのポジションを明確にでき、ミッション・ビジョン・バリューをより実態に沿ったものにすることが可能です。
3Cとは「Customer(顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3つの要素のことで、それぞれ下記のように調査・整理します。
◼︎Customer(顧客)
- どんな課題を抱えているのか
- その課題を解決するために、どんな製品・サービスを利用しているのか
- それらに対してどんな不満を持っているのか
- お金を払ってでも欲しい製品・サービスは何か
- どんな価値観・ライフスタイルを持っているのか
- 顧客のセグメンテーション
◼︎Competitor(競合)
- 顧客の課題を解決するために、どんな製品・サービスを提供しているのか
- 顧客はそれをどう評価しているのか
- 自社の強み・弱みは何か
- 業界内で自社はどのポジションを狙うのか(ポジショニング戦略)
◼︎Company(自社)
- 現状の事業・製品・サービス・ブランドの定義
- 目的達成のために強化すべきことは何か
これらを踏まえて事業領域を整理すれば、MVVの方向性をより現実的かつ解像度高く描くことができます。
社員の意見を取り入れる場を設ける
MVVを策定するうえで欠かせないのが、社員の意見を取り入れることです。経営層だけで決めてしまうと一方通行になり、組織全体に浸透しにくくなります。
経営層がつくった価値観の仮説をもとに、全社員を対象としたワークショップを実施し、現場の意見や日々の行動規範を掘り起こします。
そこで得られた内容を経営層が整理・精査すれば、組織全体で納得感のあるバリューへと落とし込むことが可能です。結果として、社員一人ひとりがMVVを自分ごととして理解し、実践につながります。
MVVを策定する際に押さえておくべき5つのポイント

価値あるMVVを策定するためのプロセスについても紹介しましたが、そこに加えて「5つのポイント」を押さえておくと、より価値のあるMVVを作れる可能性が高まります。
続いて、MVVを策定する際に押さえておくべき5つのポイントを紹介します。
1.ミッション・ビジョン・バリューの一貫性を持たせる
MVVを策定するうえで重要なのは、それぞれに一貫性を持たせることです。3つがばらばらでは、社員もステークホルダーも方向性を理解できず、組織に根づきません。
- ミッション … 組織が存在する理由や使命であり、日々の行動指針
- ビジョン … 組織が目指す理想の未来像で、ミッションの積み重ねによって到達を目指す姿
- バリュー … ミッションを遂行し、ビジョンを実現するために大切にする価値観
上記の3つは「使命」「未来像」「価値観」として、相互に結びついてこそ意味を持ちます。理想の未来を描き、その実現のための行動指針と価値観を一致させることが、事業成長の大きな原動力となります。
2.誰もが覚えられるシンプルな表現にする
MVVは、誰もが理解し、記憶できるものであることが大切です。特に、ミッションやビジョンは日常的に語られる機会が多いため、複雑で長い表現では浸透しにくくなります。
そのため、ミッションは一文で、ビジョンは簡潔なフレーズで表現するのが効果的です。社員がすぐに思い出せるよう、言葉のリズムやインパクトにも配慮し、頭に残りやすい情報量に絞り込むことが求められます。
3.社内外から共感を得られる表現にする
MVVに使う言葉は、全社員が理解し共感できるシンプルな表現であることが重要です。
経営層だけが理解できる専門用語や抽象的な言い回しでは、現場に浸透しません。特に、バリューは日々の行動指針となるため「どんな行動を取ればよいか」が具体的にイメージできる言葉にする必要があります。
また、MVVは社外にも発信されるため、ステークホルダーにとってもわかりやすく、信頼や共感を得られる表現であることが求められます。耳慣れない横文字や解釈が分かれる難解な表現は避け、誰にとっても理解しやすい言葉を選びましょう。
4.社会や時代の流れに合ったメッセージにする
MVVは企業内部だけでなく、社会や時代の流れを踏まえて策定することが重要です。どれほど優れた理念であっても、社会の価値観とずれていれば、共感を得られないほか、批判を招くリスクがあります。
特に、現代はネットやSNSの普及により企業のメッセージが瞬時に広がる時代です。SDGsやサステナビリティといったテーマが重視される今、これらに無関心な姿勢や、一部の価値観に偏った表現は批判される可能性があります。MVVに社会性を盛り込むことで、社会的信頼の獲得や社外ステークホルダーとの関係強化につながります。
5.社員を巻き込みながら策定する
MVVは経営層だけで決めるものではなく、社員を巻き込んで策定することが重要です。社員自身が策定過程に関わることで「自分ごと」として捉えやすくなり、組織全体への浸透がスムーズになります。
特に、社外への発信に積極的な企業ほど、社内での共感形成が欠かせません。人事や経営企画といった部門も、経営陣の意思決定を支える役割として、初期段階から関与することが求められます。正確な情報を共有しながら、経営層と連携を図ることが大切です。
縁達磨では縁起こしブランディングで商売繁盛を支援
縁達磨は、独自の「縁起こしブランディング」を軸に、戦略立案からデザイン制作、マーケティング実行まで一気通貫でお客様の商売繁盛を支援しています。
「縁起こし」とは、人・モノ・コト・場といったあらゆるつながりを引き起こし、販売効率を高めながら未来の競争力を育てる考え方のことです。
私たちは、この信念を大切にし、お客様が依頼する価値を実感できるよう支援していきます。
商売のお悩みはいつでもご相談ください
記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。縁達磨は、MVVや理念の策定を得意としている会社です。
「MVVを策定したい」「理念をもっと浸透させたい」といったお悩み事があれば、お気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら : お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら : お気軽にお問い合わせください。
Drop us a line.