
2025.09.28
MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の作り方とは?全社に浸透させる方法も紹介
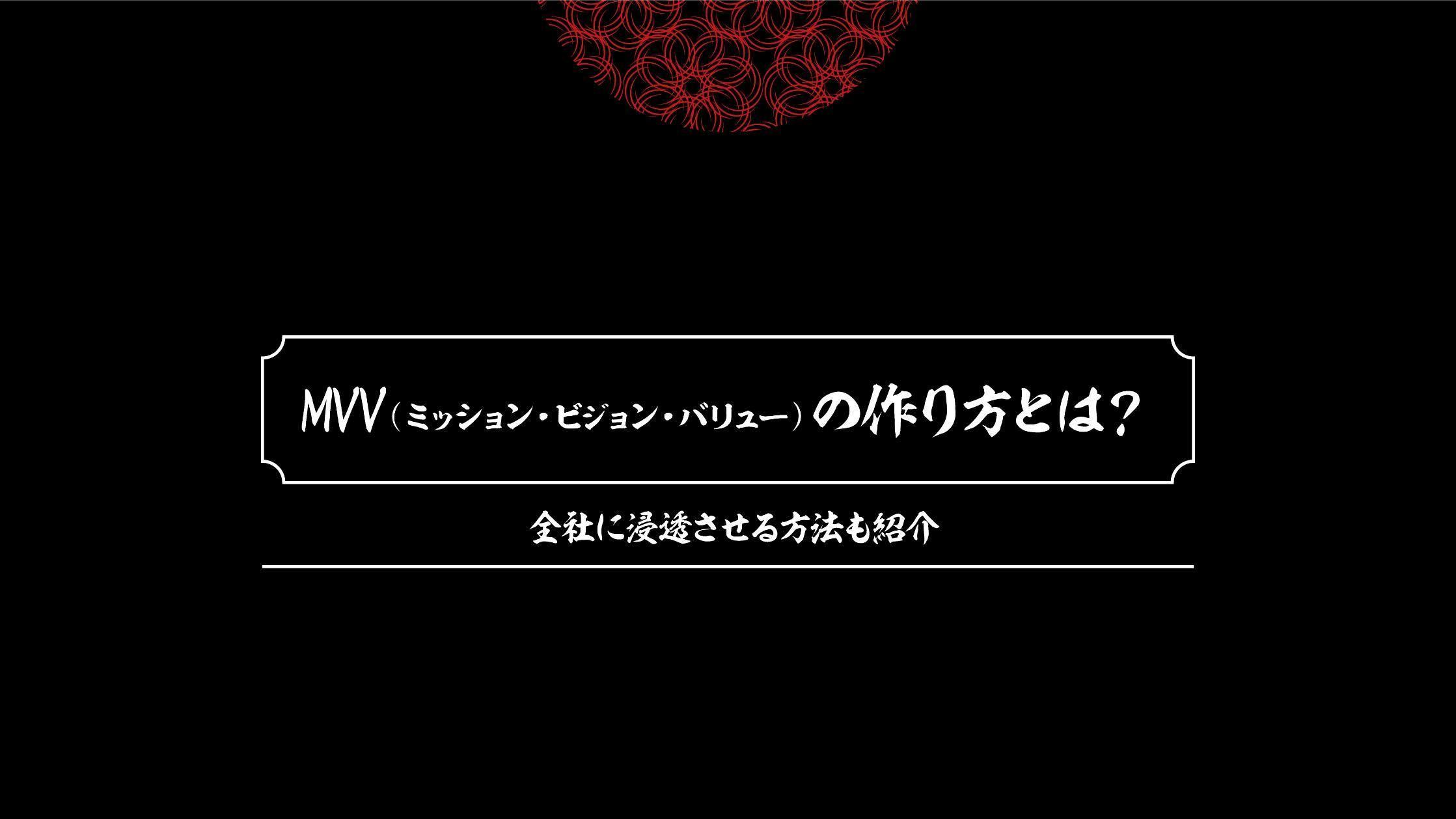
MVVは、企業の存在意義や将来像、価値観を明確に示し、組織の軸となる重要な要素です。しかし「どう作ればよいのか分からない」「せっかく作っても社員に浸透しない」と悩む企業も少なくありません。
本記事では、MVVの基本的な作り方から策定のステップ、全社に浸透させる具体的な方法などを紹介します。
MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の作り方

MVVは企業の存在意義や将来像、価値観を示すものです。ここでは、MVVをそれぞれ作る際のポイントをご紹介します。
ミッション
ミッションは、企業の存在意義を示す言葉です。作る際は「自社は何のために存在しているのか」「社会にどのような価値を提供したいのか」を検討します。
一般的には、最初に社長が自らの思いを言葉にし、それを経営陣と共有します。その後、経営陣が会社の存在意義を議論し、最終的に社長と経営陣が合意して決定します。
従業員の意見を大切にする企業や小規模な組織では、経営陣が骨子をまとめたうえで、アンケートやワークショップを通じて社員の声を取り入れる方法も効果的です。
また、作成する際は「永続性」と「普遍性」を意識してください。特定の商品やサービスに依存せず、組織が存続する限り変わらない言葉であることが大切です。最終的には、誰にでも理解できるシンプルな表現にまとめることを心がけましょう。
ビジョン
ビジョンは、ミッションを実現するために克服すべき社会課題や、理想とする未来像を描いたものです。社員が「数年後にこの未来を実現できる」と信じ、ワクワクと期待感をもって働けるような内容にする必要があります。
例えば、ミッションが「すべての子どもに平等な学びの機会を届ける」であれば、ビジョンは「全国の小中学校にオンライン教育を普及させる」といったものになります。
また「2030年までにすべての小中学校の生徒が1人1台タブレットを利用できる環境を実現」といった数値目標を盛り込むことも有効です。
ビジョンは、自社の競争力や短期的に目指したい方向性を踏まえてまとめましょう。可能であれば、従業員共通の「合言葉」となるような表現を目指すのがおすすめです。
バリュー
バリューを作る際は、まず経営層が「理想的な社員像」を思い描きます。そこから、社員がどのような価値観や行動を日常的にとるべきかを洗い出していきます。
次に、現場の従業員を交えてディスカッションを行い「どうすればミッションやビジョンを実現できるのか」というテーマで意見を収集します。
そこで出てきたキーワードを整理し、最終的に3〜5個程度のバリューにまとめます。数が多すぎると覚えにくく浸透しないため、シンプルで再現性のある言葉に絞ることが重要です。
また、各バリューには具体的な行動指針をセットにして定義すると、社員が日常で活用しやすくなります。例えば「スピード感」というバリューに対して「即日対応を徹底する」といった行動を示すことで、現場での再現性が高まります。
MVVを作る際のステップ

MVVを作る際は、以下で紹介する6つのステップを辿ることをおすすめします。
全てのステップを踏む必要はありませんが、いくつかのステップを飛ばしてしまうと、後のステップで苦労することになるので注意が必要です。
現状分析を行う
MVVを実効性のあるものにするためには、まず組織の現状を正しく理解することが欠かせません。特に、自社が市場の中でどのような位置づけにあるのかを把握することが重要です。
例えば、自然食品市場を想定した場合、自社の強みとして「高品質な製品」や「スタッフの専門知識」が挙げられるでしょう。一方「価格競争力の不足」や「ブランド認知度の低さ」といった弱みが見えてくるかもしれません。
このように、強みと弱みの両面を洗い出し、市場や競合と比較することで、自社が本当に発揮すべき価値や、今後補うべき課題が明確になります。
関係者からの声を集める
ミッションやビジョンを検討する際は、経営層だけで完結させるのではなく、社内外の関係者からの意見を集めることも重要です。
従業員や顧客、投資家、さらには地域社会まで、それぞれが何を重視し、どのような期待を持っているのかを理解することが、実効性のある指針づくりにつながります。
例えば、顧客からは「環境に配慮した製品をもっと増やしてほしい」という声が出るかもしれません。従業員からは「挑戦を後押しする文化を大事にしてほしい」という要望が挙がることもあります。
投資家は「持続的な収益基盤の確立」を重視し、地域社会からは「地元雇用や社会貢献活動への期待」が寄せられることもあります。
こうした多様な意見を汲み取って整理することで、策定したMVVは机上の空論ではなく、現実に根ざした、共感を得やすいものになります。
ミッションを明確化する
ミッションは「私たちは何のために存在しているのか?」という問いに対する答えであり、企業の存在意義を示すものです。
ビジョンやバリューに比べて抽象度が高いため策定が難しく、時間をかけて議論を重ねる必要があります。経営理念や企業理念と呼ばれることもありますが、基本的な意味は同じです。
ビジョンを描く
ビジョンは、企業が将来どのような未来像を達成したいのかを示すものです。ミッションで定義した存在意義を前提に、その延長線上で数年後に実現したい理想の姿を表現します。
ビジョンは単なる目標ではなく、企業の志を象徴するものです。理想の未来像を共有することで、組織全体の一体感を高め、日々の活動に方向性と意味を与えます。
バリューを定義する
バリューを定義する際には、企業が重視する価値観や行動基準を明確に言語化することが求められます。これは組織文化を形づくり、社員の判断や日常の行動に直結する重要な要素です。
まず、ミッションやビジョンを踏まえて大切にすべき価値観や行動基準の仮説を立てます。次に、その仮説が実際の業務や文化に適しているかを検証します。特に、ミッションやビジョンとの一貫性を持たせることが欠かせません。
最後に、全社員が理解しやすく、日常で使える言葉へと磨き上げます。抽象的すぎず、具体的すぎない表現に整えることで、現場に浸透しやすいバリューとなります。
全社への浸透を図る
新しいMVVを策定した後は、それを全社に浸透させることが重要です。単に掲げるだけではなく、社員一人ひとりが理解し、自らの行動に結びつけられるようにする必要があります。
そのためには、まず経営陣が率先してMVVを語り、日々の意思決定や発言の中で繰り返し示すことが必要です。
また、共有の場を設けることも効果的です。社内イベントやタウンホールミーティング、研修などを通じてMVVを伝え、社員が自分の言葉で説明できる状態にしていきましょう。
社内SNSやニュースレターなど日常的なコミュニケーション手段を活用することで、継続的に意識づけを図ることもできます。
最終的に、評価制度や目標管理といった仕組みにMVVを組み込み、日常業務に自然に紐づけていくことが理想です。
MVVを作る際に押さえておくポイント

ここまでMVVを作っていくうえでの具体的な方法論やステップについて解説してきましたが、ここからはそれらを実践していく上で大事にして欲しいポイントを紹介します。
このポイントを押さえておかないと、社内外の関係者から「理解・共感できない」と言われてしまうかもしれません。
それでは、一つずつ詳細に見ていきましょう。
誰が読んでも理解できる表現にする
MVVは社内だけでなく社外のステークホルダーにも伝えるものです。そのため、誰が読んでも理解できる表現にすることが不可欠です。
特に、ミッションやビジョンは、難解な言葉を避け「小学六年生でも理解できる表現」にすることが理想とされています。
もし表現が複雑すぎると、近い意味を持つ言葉をつなぎ合わせて誤って解釈され、本来伝えたいイメージが正しく共有されなくなる恐れがあります。
社内では通じても、社外の人には正しく伝わらない可能性があるため、専門用語や社内略語を使用する場合は特に注意が必要です。
実現可能な目標にする
ビジョンは挑戦的であることが理想ですが、同時に非現実的なものであっては意味がありません。
例えば「地域で最も選ばれる学習塾になる」といった表現は、努力と時間をかければ達成可能であり、現実的かつ挑戦的なビジョンの好例と言えます。
理想を掲げつつも、現状とのギャップをどう埋めるかを考え、実現可能な範囲に落とし込むことが大切です。
現実的な道筋が描けるビジョンであれば、社員の共感や行動を促し、組織全体が一体となって目標達成へ進めます。
社員を巻き込んで当事者意識を高めてもらう
MVVは経営陣だけで決めて伝えるのではなく、できる限り多くの社員を策定プロセスに巻き込むことが大切です。
自分の意見が反映されていると感じられることで「参加している」という感覚や「自分たちのもの」という所有感が生まれ、MVVへの共感と主体的な取り組みにつながります。
また、バリューや行動指針を運用する際には「この行動はどのバリューにつながるのか」と明示し、日常の行動と結びつける工夫が欠かせません。
定期的に見直してアップデートする
MVVは一度策定して終わりではなく、運用しながら継続的にブラッシュアップしていくことが大切です。
例えば「価値を十分に提供できていない」「新たな競合が台頭した」といった理由から、見直しが必要になるケースは少なくありません。定期的に再確認し、必要に応じて更新することをおすすめします。
MVVを作った際に全社へ浸透させる方法

MVVが完成したら、次の課題は全社への浸透です。ここでいう「浸透」とは、すべての社員が理解し、思考や行動の基盤として活用できる状態のことです。
以下に、いくつか具体的な施策を紹介します。
日常的にMVVを意識できる環境を整える
MVVを全社に浸透させるには、社員が日常的に意識できる環境づくりが欠かせません。
MVVを組織のウェブサイトや社内文書、ポスターなどに掲載し、常に視認できる状態にしておきましょう。繰り返し目にすることで、社員は自然とMVVを意識できるようになります。
定期的なミーティングや社内イベントでMVVをテーマにしたディスカッションを行うことも効果的です。さらに、社内ニュースレターやメールマガジンで関連する成功事例を紹介すれば、実際の業務とのつながりを実感しやすくなります。
社員が自身の業務に、どのようにMVVを活かしているかを共有できる場を設けることも有効です。社内ブログやSNSを通じて取り組みを発信することで、MVVが単なるスローガンではなく、実践的な指針であることを伝えられます。
経営陣・管理職が日々の行動で体現する
MVVを全社に浸透させるには、経営陣や管理職が自らの言動で体現することが欠かせません。
リーダーがMVVを基準に意思決定を行い、その行動が一貫して理念と結びついていれば、従業員に強い信頼と説得力を与えます。単に掲げるだけでなく、リーダー自身が日常的にMVVを口にし、具体的な行動で示すことが浸透の近道です。
研修を通じて理解を深めてもらう
MVVを全社に浸透させるには、定期的にMVVをテーマにした研修を実施することが効果的です。
特に、新入社員のオリエンテーションや定期研修の場で繰り返し教育することで、社員一人ひとりが自分ごととして捉えやすくなります。
研修では、MVV策定時に行った「関係者からの声を集める」プロセスを再現します。
例えば、社員をグループに分け、ミッション・ビジョン・バリューのテーマについて議論し合うことで、理解を深めると同時に組織への愛着も育まれます。
また、MVVが日常の行動や意思決定にどう影響するのかを、具体的な事例を交えて説明するとさらに効果的です。
評価制度に反映させる
ミッション・ビジョン・バリューを人事評価制度の基準として公表すると、社員は自分ごととして捉えやすくなり、自発的に行動するようになります。
抽象的な理念だけでなく、具体的な行動基準に落とし込むことが重要です。例えば「チームワークを大切にする」というバリューであれば、評価項目には「メンバーとの協働姿勢」や「情報共有の積極性」など、観察可能な行動を設定します。
また、従業員の評価や昇進、報酬の根拠にMVVを取り入れることで、社員にとっての具体的なメリットが生まれます。自己の利益に直結する仕組みとすることで、MVVを実践する強い動機付けにつながります。
習慣化し、文化として根付かせる
MVVを全社に浸透させるためには、制度や仕組みを整えるだけでは不十分です。制度はきっかけを与えますが、それだけでは「制度疲れ」を起こし、定着にはつながりにくいからです。
そこで重要になるのが「文化」です。ここでいう文化とは、日々の小さな言動や習慣の積み重ねを指します。相手を思いやる姿勢、挑戦を称賛する雰囲気などが代表例で、こうした行動が繰り返されることで自然に文化が育まれていきます。
つまり、制度や仕組みを通じて望ましい行動を促し、その行動が積み重なって文化を形成します。MVVを浸透させたいのであれば、「MVVを体現する行動を文化として定着させる」視点が欠かせません。
縁達磨では縁起こしブランディングで商売繁盛を支援
縁達磨は「縁起こしブランディング」を中心に、企業の商売繁盛を支援しています。
MVVの策定や再構築を含むブランディング支援も数多く手掛けており、単なる販売促進にとどまらず、ブランド戦略からマーケティング実行までを一貫してサポートしています。
商売のお悩みはいつでもご相談ください
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
縁達磨では、MVVの策定や浸透だけでなく、ブランド戦略、新商品・サービス開発、リブランディングなど幅広い支援実績があります。
また、MVVは社内に浸透させるだけでなく、社外にどう発信するかを意識して作り込むことが成功のカギとなります。
ぜひお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら : お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら : お気軽にお問い合わせください。
Drop us a line.