
2025.10.24
ブランディングとは?意味やマーケティングとの違いやをわかりやすく解説
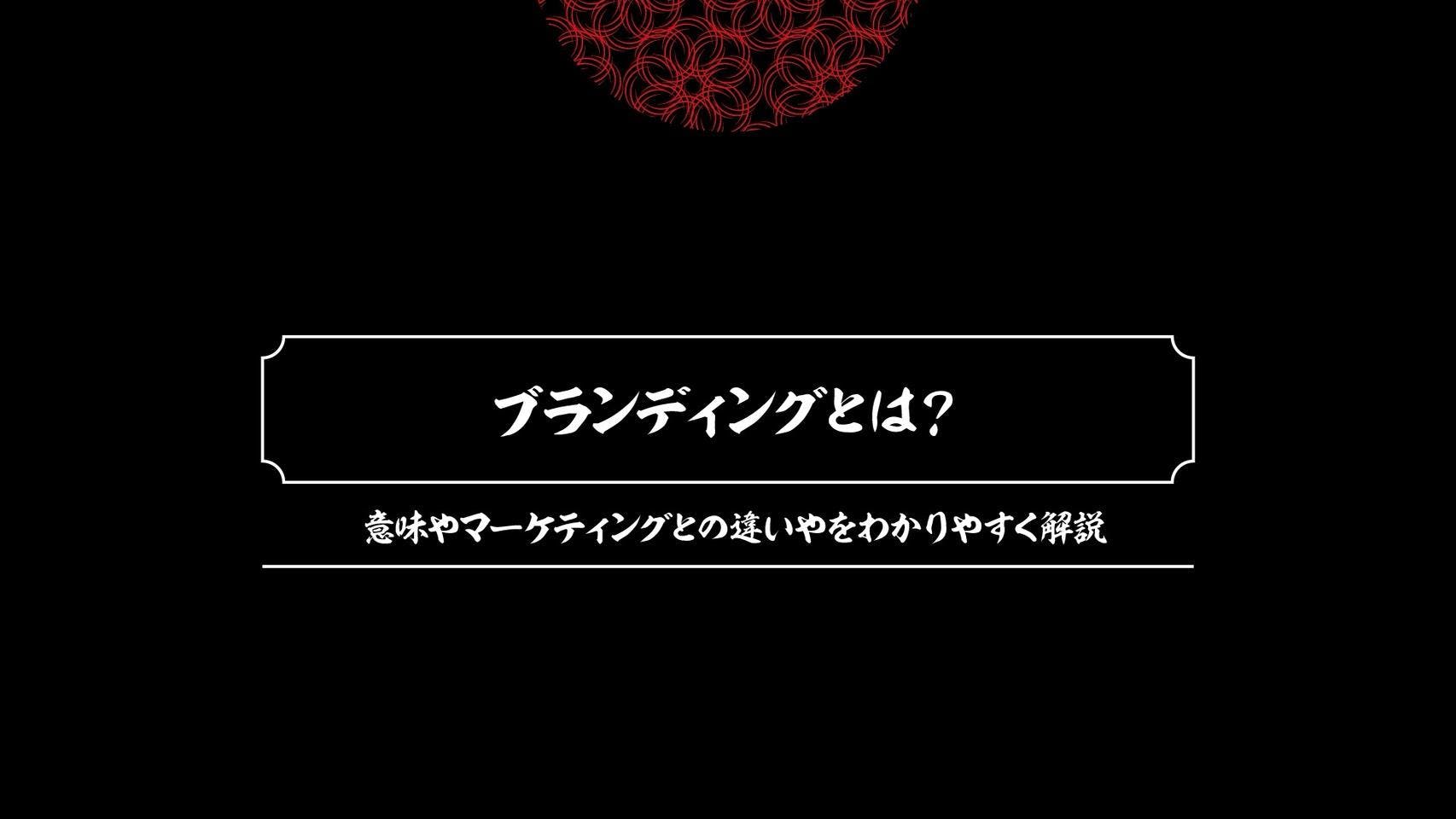
「良いものを作っているのに、価格競争に巻き込まれる」「採用やリピーターづくりが伸び悩む」といったお悩みは、ブランディングで解決できます。価格や機能で差がつきにくい今こそ「選ばれる理由」を言語化し、伝え方と体験に一貫して落とし込めるかが重要です。
本記事では、ブランディングとは何かをわかりやすく解説するとともに、マーケティングとの違いや進め方などを紹介します。
ブランディングとは?

ブランディングとは、自社が「何者か」を定め、ぶれない発信で信頼と共感を積み重ねて“選ばれる理由”をつくる取り組みのことです。ブランドは「他と区別できるもの」を意味し、 ブランディングはそのブランドを世間に浸透させる一連の活動を指します。
また、ブランディングはブランドの価値を高め、 顧客に「このブランドなら安心」と感じてもらうための施策です。 ターゲットに響く企業イメージやメッセージを発信し、 商品やサービスを「特別な存在」として記憶に残すことも重要になります。
マーケティングにおけるブランディングの役割は、認知拡大です。 例えば、ユニクロ は「LifeWear」というコンセプトで日常着の代表的な選択肢として想起されるポジションを確立しています。
ブランドを形成する要素
ブランドを形成する代表的な要素は、下記の通りです。
- ブランド名......一言で“何者か”を伝え、記憶に残す
- ブランドカラー......世界観や価値観を直感的に伝える
- ブランドロゴ......個性を象徴し、瞬時に識別させる
- ミッション......存在意義と進む方向を示す
- 開発国......「どこで作られたか」で品質への信頼を抱かせる
- 特徴......競合と比べた際に「このブランドを選ぶ価値がある」と感じさせる
- 広報キャラクター......親近感を生み、想起を後押しする
- パッケージデザイン......手に取る瞬間の体験で、価値を感じさせる
ブランドを形成する要素は、顧客の印象形成に直結するため同じ方向性で設計し、戦略的に組み合わせなければなりません。
例えば「ナチュラル/サステナブル」を軸にするアパレルなら、自然を想起させるブランド名、ベージュやグリーンの基調色、再生紙を用いたパッケージを揃えます。これにより、言葉・色・体験が一本につながり、消費者の記憶に残りやすくなります。
ブランディングの種類
ブランディングは、目的と対象によって狙いが変わります。ここでは「社内向け」「事業向け」「人材向け」の3種類を取り上げ、それぞれが何を高めるためのブランディングかを解説します。
社内向け(インナーブランディング)
社内向け(インナーブランディング)は、社員一人ひとりにブランド価値や企業理念を深く理解し、共感してもらうための施策です。例えば、下記などを活用し、日常的にブランドメッセージを発信します。
- 社内報.....部署をまたいだ成功事例をわかりやすく紹介する
- 社内SNS……取り組みの写真や短い動画を共有して、日常の“良い実践”を見える化する
- ワークショップ・研修......全社員が参加できる形にして「学ぶ→やってみる」までをその場で体験してもらう
- 社内イベント......頑張りを可視化する表彰制度や、社内アンバサダー(社内の伝え役)を置いて、各チームでの広がりを後押しする
こうした仕組みを組み合わせることで、自然と“応援したくなる人”が増え、チームの一体感が高まり、仕事の成果も上がります。
事業向け(商品・サービスブランディング)
事業向け(商品・サービスブランディング)は、自社の商品やサービスの価値を明確にし、顧客に「この商品を選びたい」と感じさせるための取り組みです。
商品の魅力だけでなく、デザイン・価格・体験・メッセージといったあらゆる要素を通じて、ブランドとしての信頼や好感を築きます。自社のコアな価値や独自の魅力を抽出し、顧客にわかりやすく伝えることがポイントです。
人材向け(採用・育成ブランディング)
人材向け(採用・育成ブランディング)は「この会社で働きたい」「ここで成長したい」と感じてもらうための取り組みです。求職者や社員に対して、企業の理念・文化・働く魅力を一貫して伝え、採用力と定着率を高めることを目的とします。
人材向け(採用・育成ブランディング)では、自社ならではの企業文化や働きがいを明確に打ち出し、他社と差別化することが肝要です。
ブランディングとマーケティングの違いは?
ブランディングとマーケティングは似ているものの、下記のように役割が異なります。
◾︎目的
【マーケティング】「今売る」こと
【ブランディング】「ずっと売れ続ける」こと
◾︎対象
【マーケティング】市場や商品価値
【ブランディング】企業や商品にこめた価値観
◾︎要素
【マーケティング】ヒト・モノ・カネ(施策資源)
【ブランディング】モノ=アイデンティティ(名前・意味・体験の一貫性)
◾︎主体者
【マーケティング】企業主体
【ブランディング】生活者も巻き込む共同作業
マーケティングとブランディングの最大の違いは「目的」にあります。マーケティングは特定の市場でシェアを拡大し、売れる仕組みをつくる活動です。一方、ブランディングは市場を超えて「長く愛され続ける仕組み」を築く取り組みです。
例えば、NIKEはスニーカーやウェアなど複数市場に展開しつつ「Just Do It」という理念で一貫した価値観を伝え続けています。市場に流行の波はあっても、強いブランドはその変化に振り回されません。
つまり「マーケティング=今を売る」「ブランディング=未来でも選ばれ続けるための戦略」です。
ブランディングで得られる効果

ブランディングは「価格以外で選ばれる」状態をつくり、値下げに頼らない競争力やリピーター増による売上安定、口コミ拡散による効率的な新規獲得をもたらします。
ここでは、ブランディングで得られる効果について解説します。
価格だけに頼らない競争力を持てる
ブランディングがあると、値下げに頼らずに選ばれる力が育ちます。理由はシンプルで、ブランディングが弱いと商品は「どれも同じ」に見え、安い方が選ばれてしまうためです。
一方、ブランドの考え方や物語、見た目や体験がそろっていると「この会社なら安心」「この雰囲気が好き」と感じ、値段以外の理由で選んでくれます。例えば、服なら肌ざわりにこだわり環境にも配慮しているからこのブランドにする、という選び方が生まれます。
家電なら、シンプルで使いやすく家になじむからこれを選ぶ、という判断になります。仕事用のソフトなら、導入後のサポートが手厚く安心して使えるから選ぶ、という理由になります。
こうした好き・安心・共感が積み重なるほど、値引きに頼らずに売れ続ける土台を作ることが可能です。言いかえると、価格以外の良さをはっきり伝え、いつも同じ体験で届けることが強い競争力になります。
長く付き合うリピーターを増やせる
ブランディングがしっかりしていると、長く付き合ってくれるリピーターが増えます。
好きや共感の気持ちが育つと、顧客は「またここで買いたい」と思い、同じ商品をくり返し選んだり、関連商品にも手を伸ばしたりします。その結果、安定した売上の土台ができ、口コミやSNSでの紹介も増えて新しい顧客の獲得にもつながります。
さらに、リピーターは一人あたりの購入金額が高くなることが多く、長い目で見ると合計の売上への貢献度も大きくなります。リピーター作りに力を入れることは、目先の売上だけでなく将来の成長を支える強い基盤づくりにつながるでしょう。
口コミ効果で宣伝費を軽減できる
ブランディングが整うと、口コミが自然に生まれ、宣伝費を抑えやすくなります。
ブランドに心を寄せた既存顧客は、SNSやレビューで体験を語り、第三者の声として安心感と信頼を生みます。口コミは「広告では届かない相手」にも情報を運ぶため、広告にかける割合を抑えられます。
結果として、新規顧客を1人獲得するための費用(CPA)が下がり、同じ予算でもより多く集客できます。口コミは一度火がつくと連鎖して広がるので、長期的な宣伝費の削減にも効果的です。
ブランディングの進め方

ブランディングは、ロゴや広告だけではありません。自社は何者で、どんな価値を約束するのかをはっきりさせ、その考えを一貫した見た目と言葉・体験でお客さまに届けていく、一連の取り組みです。
信頼を育て、長く選ばれるためには、感覚で進めるのではなく手順を決めて体系的に進めることが大切です。ここでは、ブランディングの進め方を紹介します。
1.自社の立ち位置を分析する
ブランド構築において、まず自社がどのような立ち位置にあるかを客観的に把握することが肝心です。フレームワークを用いれば、市場や競合との違い、自社の強み・弱みを体系的に整理できます。
下記のような代表的な手法を活用し、自社に合った分析からスタートしましょう。
◾︎3C分析
構成......Customer(市場・顧客)・Competitor(競合)Company(自社)
何をする......顧客ニーズ・競合の動き・自社の状況を並べて比較する
判断のポイント......だれに、何で、どう勝つかの方向感をつかむ
◾︎PEST分析
構成......Politics(政治)・Economics(経済)・Society(社会)・Technology(技術)
何をする......規制・景気・価値観・技術の変化を確認する
判断のポイント......市場の変化要因(追い風・向かい風)を把握する
◾︎5フォース分析
構成......競合・新規参入・代替品・買い手の交渉力・売り手の交渉力
何をする......界内の力関係と圧力ポイントを点検する
判断のポイント......利益を出しやすさと、圧力の源泉を知る
◾︎SWOT分析
構成......Strength(強み)・Weakness(弱み)・Opportunity(機会)・Threat(脅威)
何をする......内外の要因を一枚に整理する
判断のポイント......「強み×機会」で攻めどころ、「弱み×脅威」で守りどころを決める
これらのフレームワークを組み合わせて現状を可視化し、次ステップのブランド戦略設計に活かしましょう。
2.社内でブランド戦略の重要性を理解する
自社の立ち位置を分析したら「ブランド戦略とは何か」「なぜ必要か」を全員で共通理解にします。この土台があると、実行段階でのブレを防ぐことが可能です。
次に、経営層はビジョンやミッションとの関係を具体的に示し、中間管理職はそれをチーム目標と日々の行動に落とし込んだうえで、下記の取り組みを継続します。
- 経営層の定期メッセージを発信し、今期の重点と判断基準を明確にする
- 全社研修やワークショップを実施し、目指す価値と顧客体験をすり合わせる
- 部門別ガイドラインを整備し、言葉づかい・デザイン・対応方針を共通化する
- 部門横断のワーキンググループを運用し、現場の課題を共有して全社基準に反映する
これらを重ねることで、広告・商品開発・カスタマーサポートなどの施策が同じブランドメッセージで動きます。結果として、統一感のあるブランドイメージが社内外に浸透し、顧客からの信頼を高められるでしょう。
3.独自のブランドコンセプトを設計する
社内でブランド戦略の重要性を理解したら、独自のブランドコンセプトを設計します。
ブランドづくりで最も重要なのは「どんな価値を、誰に、どのように届けるのか」を一言で示すブランドコンセプトを定めることです。これが決まると、発信と言葉、体験の方向がそろい、一貫性のあるブランドへと育てやすくなります。
まず、自社の強み(USP)と顧客のニーズや価値観を整理し、重なり合う点を見つけます。次に、競合との差を明確にし、自社ならではの魅力を言語化します。こうしたプロセスを通じて「他ではなくこのブランドを選ぶ理由」を浮かび上がらせます。
例えば、アパレルなら「忙しい都市生活者に、長く着られる上質な日常服を、環境配慮の素材で届ける」といった形で、下記を短く言い切ります。
- ターゲット
- 価値
- 約束
コンセプトを一文で表せるようにしておくと、社内外に伝わりやすく、あらゆる施策の軸として活用することが可能です。
4.ブランドらしさを示すアイデンティティを明確化する
独自のブランドコンセプトを設計したら、ブランドらしさを示すアイデンティティを明確化します。
ブランドアイデンティティは「このブランドは何者で、どんな印象で覚えてほしいか」を言葉と見た目で一言にまとめる核です。これを定めることで、どの接点でも同じ“らしさ”を感じさせます。
核が曖昧だと、表現や伝え方がばらつき、顧客が覚えにくくなります。ミッション・ビジョン・バリューを一つの骨子にまとめ、その骨子に合わせてロゴやカラー、言葉のトーンを整えると、発信と体験に一貫性が生まれます。
例えば、子ども向け学習サービスなら「好奇心を育てる」を核に据え、明るい配色と丸みのあるロゴ、やさしい語り口で統一します。B2Bのセキュリティ企業なら「安心を標準にする」を核に置き、落ち着いた配色と直線的なロゴ、簡潔で信頼感のあるトーンに揃えます。
5.多角的にブランドの価値を設計する
ブランドらしさを示すアイデンティティを明確にしたら、多角的にブランドの価値を設計します。ブランドは、どれか一つに偏ると成長が止まりやすいため、下記の3つを同時に設計してバランスよく高めることが重要です。
- 顧客価値(買う人が感じる良さ)
- 資産価値(売上や認知などの成果)
- 社内価値(社員の誇りや一体感)
顧客価値だけ高くても収益や認知が伸びにくく、資産価値だけ追うと短期指標に流されて支持が弱まります。社内価値だけ高くても外への伝わり方が弱いままです。
3つがそろうと、満足→口コミと指名の増加→売上と投資余力の拡大→社員の誇りと改善意欲の向上、といった良い循環が生まれます。
6.記憶に残るブランド名とロゴを開発する
多角的にブランドの価値を設計したら、記憶に残るブランド名とロゴを開発します。ブランド名は企業の第一印象を決める大事な要素です。
名称に込めたコンセプトや価値、想いがストレートに伝わるよう、シンプルで覚えやすい言葉を選びましょう。他社とかぶる名前は避け、商標登録やドメイン取得の可否の事前確認が必要です。
ロゴは、視覚的にブランドを象徴するアイコンとして機能します。縮小表示やモノクロ利用も想定し、細かすぎないミニマルなデザインを心がけましょう。
7.効果的なブランド発信の場を決める
ブランド名とロゴを開発したら、効果的なブランド発信の場を決めます。
具体的にはウェブサイト、SNS、メールマガジン、リアルイベント、店頭プロモーション、PR記事などが該当します。まずはターゲット層の行動や情報収集の傾向をリサーチし、どの媒体に最も接触機会が多いかを把握しましょう。
リソースやコストも考慮しながら、複数のチャネルを組み合わせることで認知拡大やエンゲージメント向上につなげます。例えば、オンラインとオフラインを組み合わせたクロスメディア戦略を採用すると、さらに幅広い層へリーチ可能です。
8.ブランディングの成果を検証する
ブランディング施策を実施して一定期間が経過したら、下記の方法でブランド認知度の効果測定を行いましょう。
- アンケート調査......認知率・想起率・イメージ評価を把握
- Web解析......ブランド名検索数・サイト訪問数を確認
- SNS分析......投稿数・エンゲージメント率を確認
- メディア露出......掲載件数・インプレッション数を集計
結果をブランドコンセプトと照合し、ターゲットの受け止めとのズレを確認します。必要に応じて、ブランドリフト調査やグループインタビューで感情・潜在ニーズも把握します。
ギャップがあればメッセージやチャネル運用を見直し、PDCAを回して狙ったブランドイメージを確実に浸透させましょう。
ブランディングを高めるためのポイント

ブランドはただ存在をアピールするだけではなく、顧客の心を動かし、選ばれ続ける仕組みをつくることが重要です。 ここでは、ブランディングを高めるためのポイントを紹介します。
ユーザー目線を取り入れて差別化する
ブランディングを高めるには、ユーザー目線を取り入れて差別化しなければなりません。
自社の商品に対する強いこだわりや誇りは、ブランド形成の原動力になるものの「作り手視点」が先行しすぎると、ユーザーが本当に求める価値を見失ってしまうリスクがあります。
ブランディングは、商品を知ってもらい、手に取ってもらう流れを作るためのものです。常にユーザー目線で「本当に役立つことは何か」を考え続ける姿勢が欠かせません。
一貫性のあるブランドメッセージを届ける
ブランディングを高めるには、一貫性のあるメッセージを届ける必要があります。場面ごとに言葉やトーンが揺れると、記憶に残らず信頼も積み上がりません。同じ言葉・トーンを使い続けることで、想起が強まります。
一貫性のあるブランドメッセージを届けるには、まずブランドの核となるコピーやキーワードを設計し、社内ガイドラインとして共有します。次に、Webサイト・SNS・資料・店頭POP・接客トークまで統一ルールを徹底し、表現の揺れをなくしましょう。
自社に合った規模感でブランディングを実践する
ブランディングを高めるには、自社に合った規模感で実施する必要があります。
規模に見合わない大型施策は費用対効果が落ちやすく、逆に身の丈に合ったチャネルへ集中すると、一貫性と継続性が生まれて成果に直結します。
例えば、大企業ならテレビCMや交通広告、大型イベントで一気に想起をつくりつつ、社内向け施策で“らしさ”を全社に浸透させます。
中小企業・スタートアップなら、SNS広告やメール、ウェビナーや展示会セミナーに的を絞り、LPや資料DLまでの導線を磨いて深く届けます。
地域密着型の事業であれば、地元メディアへの寄稿や店頭体験イベント、商店会との連携といった近距離チャネルで接点を増やし、口コミを育てます。自社に合う規模感で運用するほど、限られた資源でも成果を積み上げやすくなるでしょう。
縁達磨では縁起こしブランディングで商売繁盛を支援
縁達磨では、縁起こしブランディングで商売繁盛を支援しています。
私たちは、ブランディングを“長く選ばれ続けるための仕組みづくり”と考えています。欲しいと思った瞬間にまず思い出してもらい、指名で選ばれる状態を目指します。
直近では老舗うなぎ店のリブランディングで、VMVの再設計に加え、商品開発や価格見直しを含むポートフォリオ戦略まで伴走しました。課題の整理から実装まで、どうぞお気軽にご相談ください。
商売のお悩みはいつでもご相談ください
ブランディングは、価値と約束を一貫して届け、購入の瞬間に真っ先に思い出される「第一想起」を獲得するための取り組みです。
社内外でブランディングを定着させるには、自社の立ち位置を分析し、ユーザー視点を取り入れた一貫性のあるメッセージを設計する必要があります。
縁起こしブランディングは、短期的な販促だけではなく、長期的な競争力強化まで実現可能です。価格競争に依存せず、リピーター増加や口コミ拡散による宣伝費削減といった効果も期待できます。
商売のお悩みやご相談はいつでもお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら : お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら : お気軽にお問い合わせください。
Drop us a line.