
2025.09.28
タグラインは商標登録できる?2016年4月の改定後の審査基準も紹介
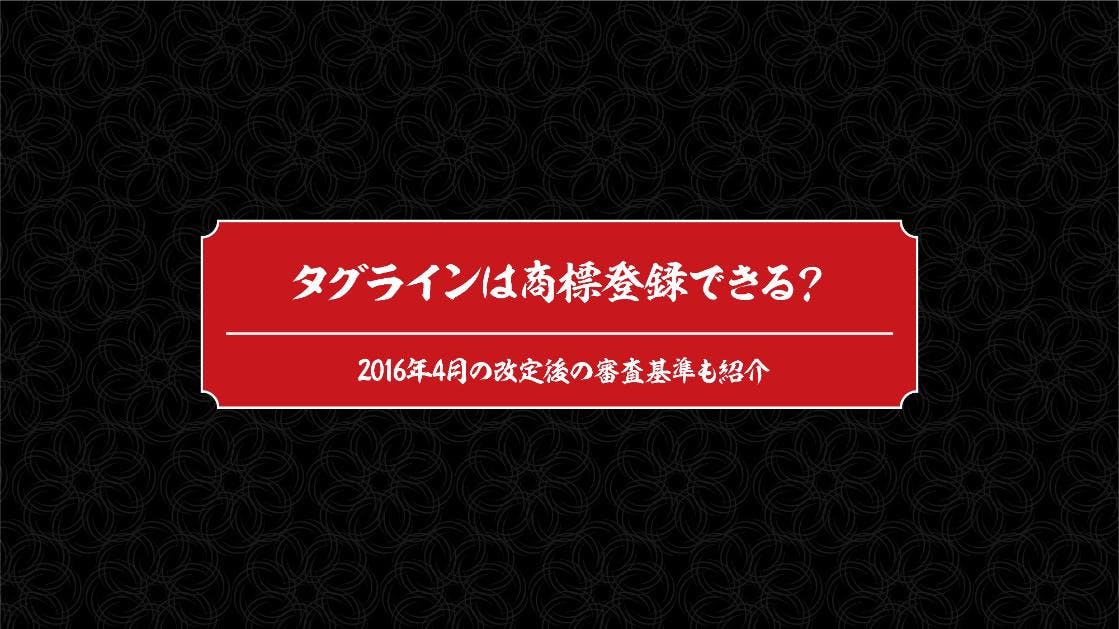
企業やサービスの印象を端的に伝えるタグライン。近年ではブランド戦略の一環として、商標登録をしたいと考える企業も増えています。しかし「本当に登録できるの?」と疑問を感じる方もいるでしょう。
本記事では、タグラインが商標登録できるのかを解説するとともに、登録のメリットや2016年4月の改定で変わった審査基準についても紹介します。
タグラインは商標登録できる?

2016年4月に商標登録の審査基準が改定されて以降、タグラインも条件を満たせば商標登録が可能になりました。ただし、全てのタグラインが登録できるわけではなく、最終的には特許庁での先行商標調査や審査によって可否が決定されます。
商標法第2条では、商標を「文字、図形、記号、立体的形状、またはこれらの結合、さらには色彩との結合も含む標章であって、自他商品・役務を識別するもの」と定義しています。
参考:商標法 第2条
この定義の通り、タグラインも自社の商品やサービスを識別できる力(識別力)があれば商標として認められます。そのため、ロゴと結合しなければならないという決まりはありません。
一方、単なる宣伝文句や一般的な表現だと識別力が弱いと判断され、登録が難しいケースが多いのも事実です。
タグラインを商標登録するメリット

タグラインを商標登録することのメリットは、主に下記の3つです。
ブランドの独占使用が可能になる
タグラインを商標登録すると、商標権が発生し、他社は同じ表現を自由に使えなくなります。これを「排他権」といい、商標制度のもっとも基本的な効力です。
独占的に使用できることにより、自社ブランドを明確に差別化し、市場での地位を固めやすくなります。
類似表現の無断使用を防げる
商標登録は、同一の表現だけでなく、類似する表現を第三者が新たに商標登録したり、事業に使ったりすることを防ぎます。
特に、日本は「先願主義」を採用しており、最初に出願・登録した企業に優先権が与えられるため、早めの出願が重要です。こうした防衛的な役割によって、ブランドを模倣から守る効果があります。
企業価値や信頼性の向上につながる
商標登録は単なる法的な保護にとどまらず「そのフレーズは自社のものである」という公式な証明にもなります。
これにより顧客や取引先からの信頼度が増し、ブランド戦略全体の一貫性や説得力が高まります。結果として、ブランド価値が向上し、市場での競争力強化にもつながります。
2016年3月まではタグラインの商標登録ができないケースが多かった

2016年3月までは、タグラインの商標登録が認められないケースが多くありました。
当時の特許庁の審査基準では「標語は原則として商標法第3条第1項第6号に該当する」とされ、タグラインを含むキャッチフレーズは基本的に登録対象外とされていました。
これは、タグラインやキャッチフレーズの多くが商品やサービスの宣伝文句や企業理念を表すに過ぎず、自他商品・役務を識別する力を欠くと考えられているためです。
実際の裁判例でも、下記の商標は「自他商品・役務を識別する力がない」と判断され、登録は認められませんでした。
- 自動車教習所を運営する会社......習う楽しさ 教える喜び
- 居酒屋を経営する会社......新しいタイプの居酒屋
2016年4月の改定後の審査基準

改定前は、タグラインやキャッチフレーズが商標法第3条第1項第6号に該当するとされ、多くが登録を拒絶される一方、審査を通過するものや、拒絶後に審判で登録が認められるものもありました。そのため、判断基準が不明確なまま運用されていたといえます。
2016年4月の審査基準改定により、どのような場合に登録が可能かが整理され、より明確に示されるようになりました。特に注目すべきは、造語や独創的な表現が登録対象として認められやすくなった点です。
造語や独創的な表現の登録が認められやすくなった
2016年4月の審査基準改定以降、標語やキャッチフレーズでも、独創性のある造語やユニークな表現であれば登録が認められる可能性が高まりました。
審査や審判での判断がより柔軟になり、従来難しかったケースでも登録につながる事例が見られるようになっています。
特定の出所表示機能を持つ場合は有利
商標の本質的な役割は、商品やサービスの提供元を示す「出所表示機能」にあります。特定の企業を自然に想起させるタグラインであれば、模倣や不正使用に対して強力な保護を受けやすくなります。
一方「セロテープ」のように一般名称化すると識別力が弱まり、保護が難しくなるため注意が必要です。
説明的・汎用的な文言は難しい
ありふれた感情表現や理念的なフレーズなど、誰でも使える説明的・汎用的な文言は商標法第3条第1項第1号により識別力がないとされ、登録が難しいと判断されるケースが多くあります。
近年は柔軟な判断も増えていますが、事例ごとに扱いが異なるため慎重な検討が欠かせません。
縁達磨では縁起こしブランディングで商売繁盛を支援
縁達磨は、商売繁盛の縁を引き起こすことを使命とし、ブランド戦略の策定からウェブサイトや動画などのクリエイティブ制作まで、一気通貫でご支援しています。
さらに、タグラインの開発をはじめ、企業の目的や課題に合わせたブランディング施策を幅広く展開し、持続的な成長を後押しします。
商売のお悩みはいつでもご相談ください
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
縁達磨では「縁起こしブランディング」をテーマに、ロゴやタグラインなどブランドの基盤づくりを一気通貫で支援しています。
「新しいブランドを立ち上げたい」「既存ブランドを見直したい」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら : お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら : お気軽にお問い合わせください。
Drop us a line.