
2025.10.24
企業ブランディングとは?目的や進め方、向上させるポイントについて解説
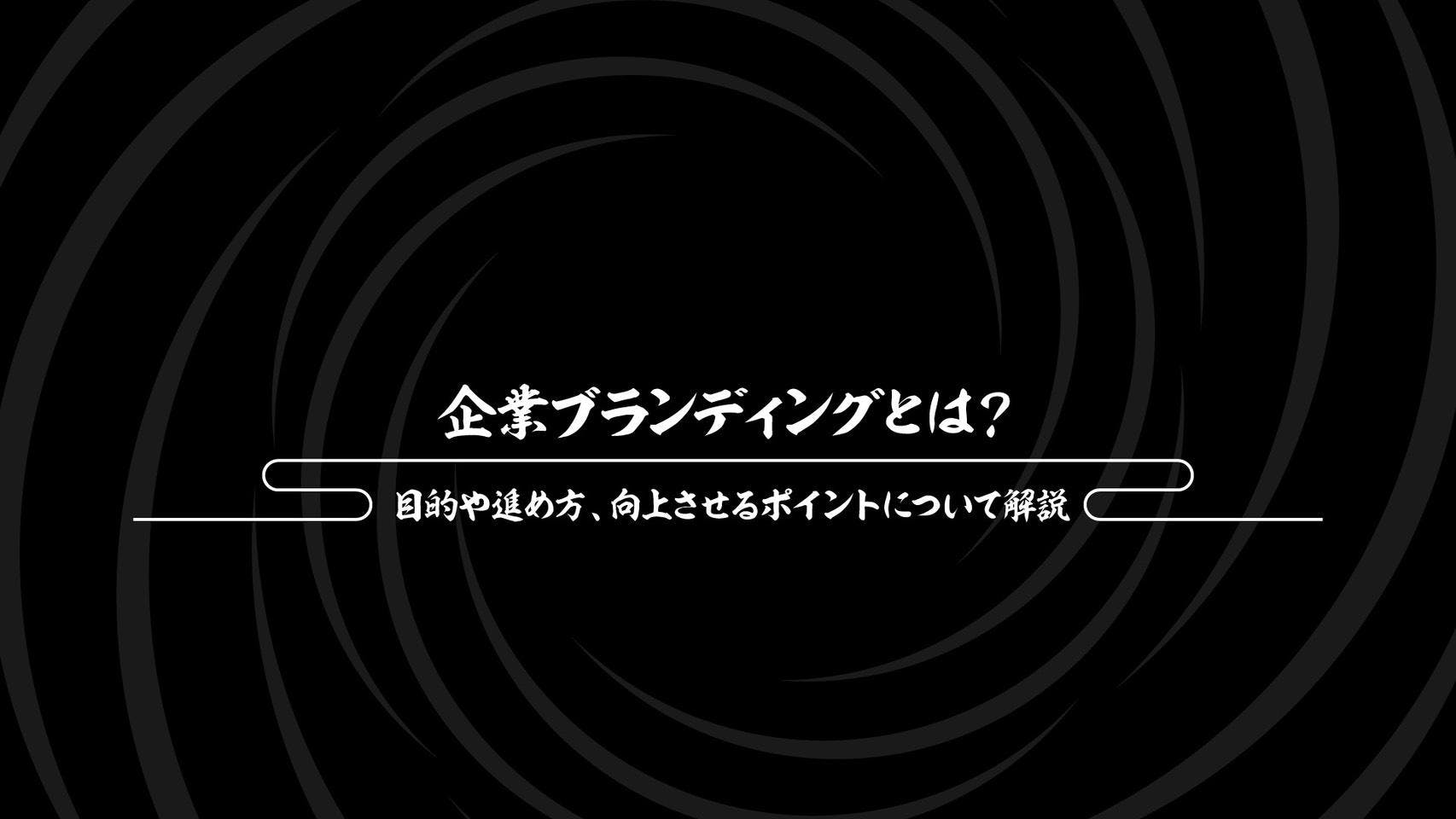
「価格競争に巻き込まれ、採用やリピーターづくりが思うように進まない」そのような悩みは企業ブランディングで解決できます。良いものを作っているのに選ばれない原因は、“価値の伝わり方”にあるのかもしれません。
本記事では、企業ブランディングとは何かや目的、向上させるポイントなどを解説します。
企業ブランディングとは

企業ブランディングは、 企業が「どんな存在で、何を大事にしているのか」を明確にし、その姿を一貫して伝えることで社会的イメージを高める取り組みです。具体的には、企業の下記の内容を発信します。
- 理念
- ミッションステートメント
- 価値観
- 企業風土
- 伝統・文化
- 強み
このイメージは、採用や広報、商品・サービスの提供、顧客対応など、あらゆる接点での体験から形づくられます。
企業ブランディングを行う目的
企業ブランディングの目的は、顧客や取引先、求職者から「選ばれる存在」になることです。市場の成熟が進む中で、似たような商品やサービスが溢れています。
そのため、機能や価格で勝負するだけでは限界があり「なぜこの企業を選ぶのか」という理由を築くことが不可欠です。
ブランドを通じて自社の理念や価値観を一貫して発信することで、顧客の共感を得やすくなり、長期的な関係性の構築にもつながります。
例えば「高品質」「誠実なサポート」「持続可能な社会づくりへの貢献」といったメッセージを軸に打ち出せば、同業他社との差別化が図れます。また、理念やストーリーを発信することで、取引先や投資家、社員など多方面からの信頼も高まります。
結果として、売上や採用力、社員のモチベーション向上といった組織全体への好循環が生まれるのです。
企業ブランディングの進め方

企業ブランディングの進め方は、大きく4つのステップで構成されます。ここでは、企業ブランディングの進め方を紹介します。
1.自社の現状を把握する
自社の立ち位置を正確に把握することは、ブランディングの第一歩です。自社の現状を把握する際は、下記のフレームワークで分析するのがおすすめです。
- PEST分析(政治・経済・社会・技術):外部環境の変化を把握する
- 3C分析(自社・競合・顧客):市場特性、顧客ニーズ、自社の強み/弱みを洗い出す
- SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威):社内外の要因を照らし合わせ、課題と打ち手の優先順位を決める
また「ブランド・エクイティ」の認知・知覚品質・ブランド連想・ロイヤリティも評価し、顧客視点での強みと弱みを明確化します。 これらの分析結果をもとに、次のステップでブランドの方向性を定めるための土台を築きましょう。
2.ブランドの方向性を定める
自社の現状分析を終えたら、次に描くのは「ブランド・ポジショニング・ステートメント」です。 これは「誰に」「どんな市場・手法で」「どんな価値を提供し」「なぜそれが実現できるのか」を一言でまとめる枠組みです。
策定にあたっては、自社の特徴や社会的役割、ビジョン・ミッション、ブランドのパーソナリティを土台に、提供価値を明確に言語化します。 さらに、大切なのは顧客や取引先など外部が共感するだけでなく、社員自身が誇りをもって支持できるかどうかです。
アウターブランディングを実現するのは社員の行動ですから、全社一体で共有し、日常業務やコミュニケーションに落とし込むことが成功の鍵となります。
3.ブランドを伝えるチャネルを選ぶ
ブランドコンセプトが固まったら、まず届けたい相手を具体化します。
年齢・性別・職業といった属性だけでなく、普段よく使うメディア(Google/Instagram/紙チラシなど)や、よく足を運ぶ場所(店舗・展示会・地域イベント)まで書き出します。これにより「どこで出会える相手なのか」を明確にできます。
次に、どこで・どう伝えるかを決めます。下記のように候補は多彩ですが、相手が普段見ている場所を優先し、目的に合う手段に絞るのが基本です。
- Webサイト
- SNS
- 広告
- 紙カタログ
- メール
- 店舗
- 展示会
- PR
- イベント など
例えば、認知を広げたいなら動画やPR、比較検討を後押ししたいなら記事や資料、体験価値を伝えたいなら店舗や展示会が有効です。
最後に、各チャネルでの発信内容やスケジュール、KPIを設定します。誰が、いつ、何を、どのように届けるのかを具体化し、効果測定と改善サイクルを組み込めば、ブランドメッセージが的確に届くようになります。
4.施策を実施し、改善を重ねる
計画に沿って、選んだチャネルでコンテンツを公開し、ブランドメッセージを発信します。実施後は必ず定期的に効果を計測し、下記の指標で変化を確認します。
- アンケート(想起・好意・推奨意向の変化)
- Web 解析(訪問数・滞在・指名検索)
- SNS(リーチ・エンゲージメント)
- 反響(問い合わせ・資料DL・来店)
また、ヒアリングやインタビューで得られる定性データを組み合わせると、顧客が感じている期待や課題がより鮮明になります。
月次や四半期ごとにレポートを作成し、KPIと照らし合わせながら社内で共有することで、担当者間の情報ギャップも解消できます。検証結果を基にした継続的な改善が、ブランドの成長を後押しするでしょう。
企業ブランディングを行う際の課題

企業ブランディングは、中長期的に企業価値を高める強力な手法ではあるものの、一筋縄ではいかない側面も多く存在します。ここでは、企業ブランディングを行う際の課題について紹介します。
成果が出るまでに長期的な投資が必要になる
ブランドが生活者の心に根づくには、広告やコンテンツだけでなく、接客・サポートなどの顧客体験や各タッチポイントの整備まで含めた継続投資が欠かせません。短期のROI最適化を優先しすぎると、価値の蓄積が追いつかず、成果の可視化も遅れます。
特に、BtoBや高価格帯(設備機器、SaaS、採用支援など)では検討期間が長く、数か月〜数年単位の計画が前提です。社内にブランドを根づかせるには、社員教育と組織風土づくりにも力を入れることが重要です。
KPIはPVやエンゲージメントに加え、下記のような“成果に近い指標”も追い、次で計測し四半期で見直す改善サイクル(PDCA)を回しましょう。
- 指名検索
- 問い合わせ・見積依頼
- 商談化率など
競合が多い市場では差別化が難しい
成熟市場で選ばれるには、自社だけの提供価値(USP)を明確にし、それを一貫したストーリーと適切な絞り込み戦略で届ける必要があります。
同質化が進む市場では、機能や価格の列挙だけでは違いが伝わりにくく、競合・顧客・自社の把握が浅いままだと価値提案が曖昧になるためです。
まずは、競合の強み・弱みを整理し、自社だけの提供価値(USP)を明確にしましょう。次に、ターゲットの具体的な悩みや状況に合わせて「課題→提供価値→証拠」をセットで提示できるブランドストーリーを設計します。
さらに、業界・用途・価格帯・地域などで絞るニッチ戦略を採用すれば、大手と正面衝突せずに独自ポジションを築くことが可能です。
これらを一貫して進め、指名検索・問い合わせ・見積依頼などのKPIで検証しながら磨き込むことで、競合が多い環境でも着実に認知と選択率を高められます。
目に見えにくい価値のため効果測定が難しい
企業ブランディングは顧客の信頼やロイヤリティなど“目に見えにくい価値”を育む活動です。そのため、短期的に成果が数値化されにくく、投資対効果の検証が難しくなります。
なお、Web施策なら指標を設定しKPIを追うことで可視化が可能です。下記の項目を月次で定点観測します。
- SEO……狙うキーワードの検索ボリュームや掲載順位、クリック率
- SNS……エンゲージメント率やフォロワー増加数
- メール施策......開封率やクリック率
これらのデータを組み合わせることで、ブランディング施策の効果をより正確に把握できます。
企業ブランディングを向上させるポイント

企業ブランディングは「つくって終わり」ではなく、常に市場や顧客の変化を読み取りながら改善を重ねることが重要です。ここでは、企業ブランディングを向上させるポイントを紹介します。
ユーザー視点で自社の強みを活かす
商品に誇りを持つことは大切ですが、こだわりが強すぎるとユーザー目線を忘れてしまう可能性があります。ブランディングの目的は、認知を広げ購買につなげることです。
まずはユーザーが何を求め、どんな課題を抱えているかを丁寧に把握し、自社の強みと掛け合わせることが出発点です。 具体的には、アンケートやインタビューでリアルな声を集め、ペルソナ設計やカスタマージャーニーでニーズを可視化します。
見えてきた課題に対して、自社の技術力や品質を“◯◯できる”というベネフィットに変換して打ち出しましょう。例えば「手間を省いて時短できる」「安心感を得られる」といった形で伝えると、ユーザーの共感を得やすくなります。
さらに、施策のたびにユーザーからのフィードバックを収集し、反応を分析しながら改善を繰り返すことが重要です。
ブランドコンセプトを明確に打ち出す
ブランドコンセプトは単なるスローガンではなく、自社が市場でどんな価値を提供するかを示す羅針盤です。まずは自社の強みやミッションを言語化し、誰に何を届けたいのかを明確に絞り込みましょう。
打ち出したコンセプトは、社内外のあらゆる接点で一貫したメッセージとして発信することが必須です。WebサイトやSNS、商品パッケージ、広告など、言葉遣い・ビジュアル・トーンを統一することで、ターゲットに「技術力の会社」「自然に優しいエコな商品」といったブランドの魅力が的確に伝わります。
さらに、定期的にメッセージの受け止められ方をチェックし、ズレがあればすぐに調整してください。こうして常にクリアなコンセプトを維持することで、ユーザーの心に刺さるブランドを築き上げましょう。
企業規模に合ったブランディング手法を選ぶ
企業規模や予算に応じた施策選びは、ブランディング成功の要です。大企業ならマス広告やテレビCM、交通広告を駆使し、短期間で広く認知を拡大できます。
社内向けにはインナーブランディングイベントや全社研修を組み合わせ、ブランド浸透を図りましょう。 一方、小規模企業はリソースを最適化する工夫が欠かせません。
ニッチなターゲットに絞ったSNS広告やコンテンツマーケティング、地域密着のイベント出展など、限られた予算で効果を最大化する手法を選びましょう。
ターゲットを狭めるほど、コミュニケーションの質が上がり、ブランドへの共感も深まります。 規模に合わせたロードマップを策定し、PDCAを回しながら柔軟に手法を見直せば、安定したブランド成長を実現できます。
縁達磨では縁起こしブランディングで商売繁盛を支援
縁達磨では、企業が長く選ばれ続けるための基盤づくりを支援しています。理念や価値観の再整理を通じて、企業が持つ本来の魅力や強みを再発見し、社会や顧客に一貫して伝わるブランドを育てていきます。
また、企業の現状や市場環境を丁寧に把握し、目指す方向性を明確にしたうえで、ブランドの浸透と定着に向けた取り組みを段階的に進めます。短期的な成果だけでなく、中長期的なブランド価値の向上を見据え、継続的に改善を重ねることを重視しています。
専任のコンサルタントが伴走し、経営層から現場までの共通認識を築きながら、企業の成長を支えるブランドづくりをお手伝いします。企業ブランディングに課題を感じている方は、お気軽にご相談ください。
商売のお悩みはいつでもご相談ください
企業ブランディングは一度取り組めば終わりではなく、目的設定からチャネル選定、PDCAサイクルの継続的な実践が成果を左右します。
縁達磨の「縁起こしブランディング」では、心・敵・技・体・動の五段階で企業の強みを磨き、短期的な売上安定と中長期的なブランド競争力を同時に強化します。
「何から始めればいいかわからない」「効果測定に不安がある」といったお悩みがある場合は、お気軽にご相談ください。 専任コンサルタントが伴走し、データに基づく最適解を導き出します。
お問い合わせはこちら : お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら : お気軽にお問い合わせください。
Drop us a line.